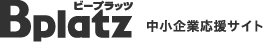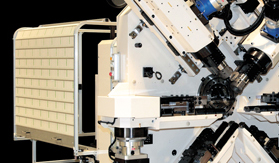手盛りならではの肉盛溶接の強みを継承し、勝ち残る

昭和36年の創業以来、肉盛溶接ひと筋に歩んできた。肉盛溶接とは、母材の鋼の上に溶材の金属を溶かして盛る加工法だ。同社は、バルブなど強い衝撃を受ける部材に対し耐摩耗性、耐食性、耐熱性などを加えるステライト合金を溶材として使う手作業の肉盛溶接、「手盛り」で一頭地を抜く。
予熱を加えた母材に、溶接機でとかした溶材を一滴ずつ落としていく。そのタイミングの見極めこそが手盛りの「命」だ。「母材が熱を持ってくると汗をかく瞬間があります。その状態になった時に一滴落とします」。“汗をかく?”「母材の鋼が溶け出す直前の状態を、こう表現し、鋼表面の色の変わり具合などで判断します」と好彦氏。一滴ごとにこの判断を繰り返す、根気のいる作業だ。
創業時から最新の溶接設備をいち早く導入。NC化の波にも対応し、肉盛溶接の自動化も並行して進める一方、手盛りの技術も守ってきた。あらゆる注文を断らず、そのたびに新たな段取り、温度管理、肉盛方法を獲得してきた。ある時、メーカーに手盛りの仕上がりを抜き打ちで検査された。母材と溶材の境界が滑らかで「自動溶接ではできない技術。組織、状態ともに完璧」と評価を受けた。
8年前、自動溶接を捨て、手盛りに特化することを決断した。4年前からは息子の守昭氏が技術を継承している。マニュアルはない。「予熱温度の目安はもちろんありますが、溶接時の母材が汗をかく状態を目で見て、自分でやってみて、先輩との出来上がりを比べながら改善する、の繰り返しです」と守昭氏。評判を聞きつけて新たな取引先も着実に増えつつある。「必ず守り抜いて、生き抜いてみせます」。守昭氏の力強い言葉に、好彦氏も横で大きくうなずいた。