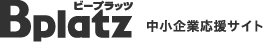コロナ禍を乗り越える「株式会社ポップサーカス」の情熱と挑戦

大きなサーカステントの入り口をくぐるとそこは別世界だ。
案内人の「It’s Showtime」のかけ声とともに、アフリカンリズムと融合した人間トランポリン、大仕掛けのマジックが展開するイリュージョンなど息つく間もなくショーが繰り広げられる。
現在はコロナ禍で休演を余儀なくされているが、ポップサーカスは今や日本に2つしかない定期公演サーカス団の一つだ。

久保田氏の父は、あるサーカス団で物販を担当し、綱渡り演者の母と結婚した。
幼少時の久保田氏は普段は祖父母の家で暮らし、夏休みや冬休みになると両親が過ごす公演先まで出かけ、団員が過ごすトレーラーハウスに寝泊まりして過ごした。
「同じ環境の幼馴染に会えるのがうれしかった。ぼくらと遊んでくれる演者も愉快な人ばかり。毎日が遊園地のようで楽しく、いつも後ろ髪を引かれていました」と振り返る。

それゆえ、父親が独立してポップサーカスを立ち上げると聞いた時は「あのワクワクした世界に加われるのか」と感じ、ホテルマンの仕事を辞しすぐに参画することができたという。今から26年前のことだ。
とはいえ全く実績のないところからのスタートゆえ、海外を含む出演者の確保、公演受け入れ先との交渉などは困難を極めた。

代表取締役社長 久保田悟氏
サーカス団といえば、演者は一生涯同じ団に所属し、メンバーは寝食を共にして暮らす家族のような集団でまさに一座のイメージが強い。だがポップサーカスは違った。
「同じメンバーだと内容もマンネリ化し、家族のようになってしまうと緊張感が薄れる」との考えから、演者は数年ごとの契約で雇用し、血を入れ替えていく手法を取った。
こうしたプロ意識の徹底が観る人を惹きつけ、ほどなく年中公演する人気サーカス団に成長した。

久保田氏が事業を承継したのは2014年。競争相手が少なくなり「ともすれば楽をしてしまいがち」な状況を戒めるため「常に満足しない」ことをモットーに掲げる。
人気のショーでもあえて打ち切り、新しいショーにチャレンジし続けるのもそうした危機感からだ。

コロナ禍により昨年2月に栃木県宇都宮市での公演を取りやめた。その後はクラウドファンディングを実施し施設維持費や再開に向けたコロナ対策費を確保。
今なお再開の見通しは立たないが「東日本大震災でも同じような経験をしており、このようなことはつきもの」と悲壮感はない。年初からは海外で暮らす演者の現状などを動画配信するなど情報発信にも力を注いでいる。
「海外ではサーカス演者はアーティストとして一目置かれる。日本でも演者の地位を上げていくことが目標」と長い目で目の肥えたサーカスファンを増やしていこうとしている。

(取材・文/山口裕史 写真/福永浩二)