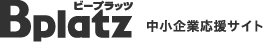利益の8割を海外で稼ぎ出す不屈の行動力

株式会社ノダが手掛ける、紙やプラスチックを打ち抜く「トムソン型(合板に刃を埋め込んだ抜型)」の業界には、30年ほど前まで国内に約1,000社が存在したが、現在では約300社にまで減少している。零細事業者が多く、激しい価格競争の中で次々に廃業を余儀なくされているのだ。その厳しい業界の中で、早くから海外に市場を求めたノダは現在、利益の8割を海外部門で稼ぎ出している。

常にコミュニケーションを大切にしている社風。
病に倒れた父の事業を急きょ引き継いだのは、野田氏が25歳の時のこと。父親がたった1人ガレージ同然の場所で行っていた抜型づくりも、廃業の道をたどっていたかもしれない。だが、野田氏は「日本一の抜型屋になる」という目標を掲げ、愛知、埼玉と相次いで生産拠点を広げていく。やがて国内市場のパイには限りがあるとみるや、おのずとその目は海外に向いた。「今度はアジアでナンバーワンになる」と。

代表取締役 野田 隆昌氏
まずは中国で事務所を間借りして、上流工程の設計図を作成し日本にデータを送るオフショア開発からスタートし、海外事業の勘所をつかんでいった。そして、2008年に初めて独資で進出したのがベトナムだ。「同業他社が少なく市場開拓の余地があったこと、そして親日的な国民性であること」を進出理由に挙げる。当初は1泊数百円の安宿に滞在し、工場までの長い道のりを自転車で通勤するという日々を過ごしながら、オフショア開発に加え、“本丸”である抜型の製造・販売にも挑んだ。
当初は赤字が続いたが、3年目に野田氏の弟が現地に駐在し、“ノダイズム”の徹底を図った。「うちが大切にしてきた企業文化である“ファミリーの絆”を重視し、社員と酒を酌み交わし、食事を共にすることで一体感を育んだ」。社員のモチベーションが向上し、離職率も減少、事業は黒字転換を果たした。また、国の制度を活用し、毎年ベトナムから5~6人の研修生を受け入れ、日本の工場でOJTを含めたトレーニングを実施、技術の定着に努めた。「当社のベトナム人技術者は、現在では各国で行われる研修に講師として参加し、日本国内での指導にもあたる程に成長しています」。

各工場での研修にも注力している(フィリピン工場)。
ベトナムに続き、2010年にはタイへ、2016年にはフィリピンへと進出を果たした。タイでは、現地の日系企業をターゲットに営業したが、ローカル企業との競争に苦戦を強いられた。そこでベトナムで培った、大量生産に適した金属加工(金型)刃型の技術を導入。木型と金型の両輪で顧客への訴求力を高め、事業を軌道に乗せていった。一方、フィリピンでは、市場こそ小さいものの、ベトナムと同様にローカル企業の競合が少ない点に着目。オフショア開発業務をベトナムからフィリピンへ移すことで1年目から黒字化を果たした。

金型刃型の製造も手がけ、現地での提案力を高めている(タイ工場)。
近年タイやベトナムで実感するのは、日系企業のプレゼンスが落ちてきていることだ。かつてのように「日系企業だから」と頼られることは少なくなり、ローカル企業や他の外資企業との熾烈な競争に勝ち抜かなければならない。その中でノダはすべての海外事業拠点で黒字化を成し遂げてきた。
「20年前、タイやベトナムに視察に出向いたときには同業他社もたくさん参加していましたが、「先例がない」「失敗したらどうする」と尻込みしてどこも進出しなかった。うちはすぐさま行動に移し、現地でバチバチやり合いながら、とことん現地の顧客のニーズに対応してきた。他社との差があるとすれば、そこで動いたかどうかです」と野田氏は語る。

会社の発展を祈願する「タンブン」(タイ工場)。野田氏も毎年参加している。
現在、同社ではすべての国内外拠点とリアルタイムで映像をつないでコミュニケーションを図れるようにしている。それを支えるのは、“ノダイズム”に裏打ちされた普段からのリアルなコミュニケーションだ。「私は1年の半分は国内外の社員との飲み会をしているし、社員交流もどんどん後押ししています」。今年は、内製で開発に取り組んできた業務システムのリリースも控えており、攻めにも守りにもDXを推進している。
「ファミリーの絆」と「デジタル化」を融合させグローバルで戦い抜いてきた先には、インドネシアやインド、さらには、メキシコや欧州も視野に入れる。27年前、たった1人で始めた抜型づくり。小さな企業ながら志を共にする人材に恵まれ、共に育ててきた雑草魂は、今、さらに世界へと広がりつつある。

各地で社員同士の交流も積極的に行われている。
(取材・文/山口裕史 写真/福永浩二)