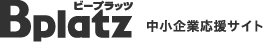壁に広がる文化の種 ミューラルでつなぐ人とまち

20世紀後半、ニューヨークの路地裏から壁に絵や文字を描く「グラフィティ」と呼ばれるストリートアートが生まれ、若者たちの自己表現の手段として広まった。近年では作品が持つ独創性から芸術としての価値が高まっている。
川添氏もヒップホップカルチャーとの出会いを通して「ミューラル(ウォ-ルアート)」に魂を射抜かれた一人だ。「自分の思いをストレートに表現する作品の力に圧倒されました」。もともと教師になる前に社会人経験をしようと企業に勤める中で、「自分の好きなことで仕事をしたい」と思うようになり、ミューラルを広める事業を着想した。

WALL SHARE(ウォールシェア)株式会社は、ミューラルを活用したいクライアントとアーティストを結びつけるビジネスモデルを展開している。クライアントの意図を汲みながらアーティストや作品の方向性は決めるが、「他人と重なることのないオリジナルを追求する」アーティストを尊重する姿勢は譲らない。
建物や施設のオーナーに掛け合って壁スペースを確保する“壁営業”も重要な仕事の一つ。「大きく、窓が少なく、見通しがいいことが条件。泥臭く飛び込みで訪ねていくことも多いですが、今では多くの人から『いい壁があるよ』と連絡をもらえるようになりました」。


ミューラルの活用法は、行政によるまちづくり、店舗装飾、企業広告の3つに大きく分類されるという。2024年のパリ五輪開催時には、大手スポーツメーカーからの依頼で柔道の阿部兄妹が戦う姿を2人の出身地である神戸の学校やビルの壁に描いた。また2024年10月には岡山県真庭市の地域協力隊からの声掛けで、スケートボードパークの床面に日本最大級となる1,000㎡のミューラルを完成させた。完成披露時には若者が企画したブレイクダンスプログラムも行われ、地域に新たな文化交流を生み出す場となっている。創業から5年で世に送り出したミューラルは約200作品に上り、直近では大手ブランドからの依頼も増えている。

ミューラルへの理解が浅く、壁を活用することに対する自治体の規制が厳しい、いわば「ミューラル不毛の地」といえる日本に、WALL SHAREがくさびを打ち込んでいるという情報は世界に広がっている。昨年はフランス人女性が「ここで働きたい」と合流。それをきっかけに、海外と日本のアーティストが相互に交流するプロジェクトが進んでいる。「日本のアニメに影響を受けた」海外アーティストから、日本で描きたいという依頼も頻繁に舞い込む。事務所を置く此花区では、銭湯や倉庫の壁を確保して海外アーティストに開放し、その作品数は30点を超えた。描くアーティストに地元のおばちゃんが差し入れをし、子どもたちが足を止める。「子どもたちにとってミューラルが“当たり前”と思う文化を日本に根付かせたい」。そんな想いを込めて今日も壁に命を吹き込んでいる。

代表取締役CEO 川添 孝信氏
(取材・文/山口裕史 写真/福永浩二)
※掲載写真は、編集部にて撮影したもの以外に、取材先企業からご提供いただいた写真も含まれています。