古くて新しい「手ぬぐい」で拓く 和モダンカルチャー

240種類の柄をそろえる手ぬぐいのブランド「kenema(けねま)」。36センチ×90センチの“キャンバス”に縁起物や季節の風物詩、動物などをモチーフにした大胆なデザインが躍る。
最大の特長は、糸の密度が細かくなめらかな肌触りの生地に「注染」という伝統工芸の染め技法を使っていることだ。「染料を生地の両面から注ぎ込むので裏表がなく、プリントで印刷するのと違って柔らかい風合いや独特な色合いを楽しんでいただける」と宮本氏は説明する。

「注染」という伝統的な染め技法。裏表が無く染め上がり、絶妙なタッチや立体感が出る。
戦後まもなくの創業。手ぬぐいや浴衣に使われる小幅綿布の製造販売からスタートし、この綿布を使ったガーゼ寝巻きなどの完成品も意欲的に開発。その後はいち早くタオルギフトを手がけるなど業界でも知られる存在となった。だか、ギフト市場の低迷とともに業績も下降線をたどる。
宮本氏が入社した2001年当時は、苦肉の策として別注品やOEMを強化しながらもがいていた。しかし、もう一度「自分たちが企画した商品を、自分たちの力でつくり売っていこう」と思い立ち、2005年に誕生したのが「kenema」だった。

季節物の商品も人気がある。右は一番の売れ筋商品「七転八起」。
ブランドの立ち上げにあたっては、海外競合品との価格競争で苦労した教訓を踏まえ「付加価値を持ったブランドとして育てていく」との考えを貫こうと決めた。これまでの古い体質を一新し、新たに企画部を立ち上げ、若手デザイナーを採用。値崩れを起こしやすい卸を通した商売を封印し、直接小売店と取引することに徹した。
卸とは商習慣、条件が異なる不慣れな小売店との商売はときに現場に混乱をもたらし、不良在庫や無理なデリバリー対応も。しかし、その中で着実に売り上げが伸びていった手ぬぐいに商品を絞り込んでいく。「kenemaに賭けた部分もあった。信じて続けようと、社内にだんだん一体感が育っていった」。

「kenema」の展示会。
そして5年目でようやく黒字化を果たす。その後、品揃えをさらに広げるため「JIKAN」「MIYAMOTO COLLECTI ON」の2ブランドを立ち上げた。前者は東京・表参道に直営店を構えるなど、小売り事業にも進出。現在では、全売上の45%が自社の3ブランドで占めるまでになった。
「社内では会社の業績復調を“kenema効果”と言っていたが、真の意味での“kenema効果”は、ベテランから若手まで全社員に、現状に安住せず変化しなくてはいけない、という意識が根付いたことだ」と宮本氏。近年は、外国人観光客が集まる観光地などでの売り上げが好調。「東京五輪に向け、インバウンドの顧客をもっと狙い海外も視野に。やるべきことはまだまだある」と次なる変化に挑もうとしている。

取締役 営業部部長 宮本 善隆氏
(取材・文/山口裕史)

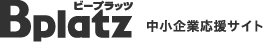









-1.jpg)