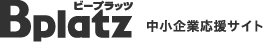脳と身体の情報伝達異常に挑むVRアプローチ

脳の機能が正常であれば、足や手などを正確に動かすことができるが、損傷や神経疾患があると思うように動かせなくなる。脳卒中やパーキンソン病などによる麻痺や運動障害がその一例だ。「脳の運動野には足、手、指などの部位ごとに神経細胞があり、協調運動を制御しています。脳の損傷や神経疾患にかかると、神経細胞と身体を結ぶ指令系統の“糸”が絡まってしまい、本来の動きができなくなったり、意図しない部位が動いてしまったりします。私たちはこうした仕組みによって情報の伝達異常が起きているのだと考えています」と原氏は説明する。
この絡まった糸をほぐす、つまり脳と身体の情報伝達異常の修復を促すために開発したのが「mediVRカグラ」だ。患者の手足の動きを3次元座標で正確に測定し、「糸」がどのように絡まっているかを把握したうえで、患者は座ったまま装着したVR(仮想現実)機器上に現れる目標に右手、左手で交互に触れるだけでよい。「第三者のサポートを受けながら手足を本来の位置に動かし、目標の位置を変えながら繰り返すことで、脳は正しい動きを再学習します」。機器を用いた場合のリハビリ効果は目覚ましく、麻痺が大幅に改善したり、歩けなかった人が歩けるようになった例も報告されている。

座った状態で装着したVR(仮想現実)機器上に現れる目標に触れるだけでいい。
2019年に機器は完成し、リハビリ機器として医療機関などへの導入をめざしたが最初の数年は年10件程度の導入にとどまった。「概念やメカニズムを説明してもなかなか理解されにくい。詐欺商法だと言われたことも何度もあります」と苦労の時期を振り返る。しかし、患者に実際に使ってもらい効果を実感してもらうとともに、海外の医学雑誌に論文を次々に発表してエビデンスを積み重ねた結果、導入施設は現在140件にまで増えている。
原氏は循環器医として、心筋梗塞の患者を多く診るなかで、脳卒中を併発し麻痺になった患者がリハビリをしても思うように回復しない現実に直面。そこから開発の道へ進み、脳の運動協調領域からのアプローチに着目するようになった。「mediVRカグラ」が画期的なのは運動野だけではなく、感覚野にも応用できる点だ。「運動は脳からの指令であるのに対し、感覚は脳へのフィードバック。例えばうつ病も“糸”が絡まっているためにどんな刺激も悲しく感じるように変換されてしまうのです」。同じように「mediVRカグラ」を使って症状軽減例も出ているという。
「シンプルに脳と身体の情報伝達の異常として病気をとらえる」。その発想は、臓器ごとに細分化が進んできた現代医療へのアンチテーゼともいえる。その着想については「さまざまな診療科を経験するように研修医制度が見直され、俯瞰できる視点を与えてもらったことも大きい」と振り返る。普及に向けてまずはパーキンソン病と、その関連神経難病で保険適用を実現し、日本国内で普及を図って収益を確立してからグローバル市場を狙う。「大阪から世界に発信し、医療界の常識を変えたい」と、原氏は力を込める。

代表取締役社長 原 正彦氏
(取材・文/山口裕史)

https://www.osaka-toprunner.jp/
◎mediVRの詳しいページは↓コチラ↓
https://www.osaka-toprunner.jp/project/medivr/