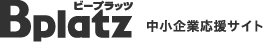新展開する畳文化、越境ECで畳の魅力を世界へ発信

日本の伝統のひとつ、畳文化が衰退している。新築住宅の和室が減少するに伴い、畳の生産量も減っている。そんな状況に危機感を覚え、海外に新たな活路を見出したのが株式会社TATAMISER(タタミゼ)だ。同社は越境ECを活用し、畳の魅力を世界に発信している。同社のサイトには天然のい草、和紙、樹脂といった素材と、カラフルな色柄の数十種類の畳が並ぶ。

「10年程前から畳の通販事業に取り組んでいましたが、ある時、補助金を受けて海外展開に挑戦しました」と代表の淡路氏。販路はシンガポールとニューヨーク。「当初は売れると思っていなかったんです。海外に住む日本人が買ってくれたらいいなくらいで」。ところが来日した時に旅館に泊まり、畳の上の敷布団で寝た経験のある海外の人たちからの反応が多く、越境ECの可能性を強く感じたという。

海外の設置事例
最初に扱ったのは琉球畳。一般的な畳に比べて薄く、半畳サイズの正方形で畳縁のないのが特徴だ。ECサイトにはおしゃれでポップな写真を掲載し、海外の人に受け入れられやすい畳の使い方を提案している。しかし淡路氏は「思いのほか手ごたえを得た一方で苦労も多かった」と話す。ひとつは高額な配送コスト。今でこそ国際宅配便が使えるが、当時は郵便局でしか送れなかったため、送料の高さをお客さまに説明するのが大変だったという。また、畳自体に対する反応もさまざまだった。湿度の高い国ではカビが生えやすいし、そもそも外国人にはい草の匂いが苦手な人が多かった。「それら畳の特徴や扱い方を、その都度丁寧に伝えることに時間をかけました」と淡路氏。

そんな地理的、文化的なギャップをひとつずつ解消し、今ではアメリカ全土、ヨーロッパ諸国、中東、オセアニアなどから注文が入る。この4、5年で海外販路の売上は約15倍にもなった。購入したお客さまから送られてきた感想や部屋の写真をサイトに載せ、SNSで発信して新たな顧客を獲得している。
伝統産業品が生き残っていくために大切なことはなにか。淡路氏は「現代のライフスタイルに合った使い方を提案すること」だと話す。「たとえば畳の場合は床暖房に対応したもの、室内でペットを飼う人に向けた洗える素材などの新しい需要を掘り起こす必要がある」と。そして、今後の海外市場については「布団メーカーと協力して畳と敷布団をセットで売ることですかね。今はそのことで頭がいっぱいです(笑)」と次の一手を模索している。

代表取締役 淡路 光彦氏
(取材・文/荒木さと子 写真/福永浩二)