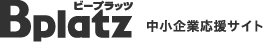組子とデザインを融合 インテリアへの挑戦が本業に還元
和室の減少や既製品の普及で厳しい状況にあった老舗建具店が、夫婦二人三脚で挑んだ商品開発。「彩り障子®」「光箱®」に続き、七宝組子をモチーフにした新シリーズ「花組子®」も注目を集め、大阪製ブランド認証やギフトショー大賞を獲得。伝統技術を活かしながら、本業にも好影響を与えた取り組みとは?新しい市場を切り拓くためのヒントを探る。

釘を使わず木片を組み合わせ、障子などを装飾する組子。伝統技術とデザインを融合させたインテリアに挑むのが有限会社種村建具木工所だ。

2019年に「大阪製ブランド」と関西広域連合のCRAFT14に認証された「光箱® 」。
1956年創業、2007年に事業を継いだ種村氏。「私が継いだ頃は和室が減少し、既製品が台頭。取引先が廃業するなど売上げが激減していました。トンネルを抜けるために打って出るには新商品が必要でした」と振り返る。妻の貞子氏と共に商品企画や自社HP立ち上げに取り組み、「彩り障子®」「光箱®」「imadoco」などを開発してきた。
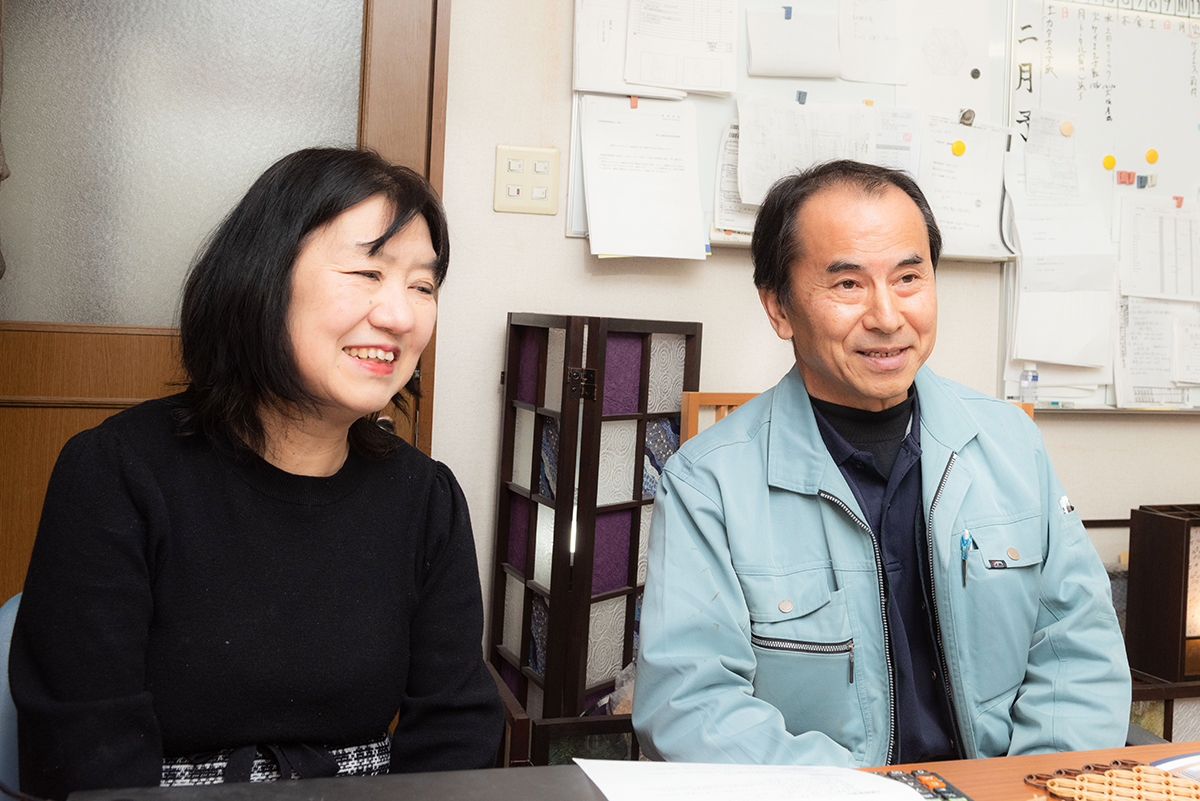
代表の種村氏と妻の貞子氏
そんな中、新たに「七宝組子」という円が連鎖する文様を取り入れた「花組子®」シリーズを展開。ライト、栃木レザーと組子のバッグ、ガラスと組子の食器プレートを衣食住になぞらえて3商品開発した。ライトは2021年に「大阪製ブランド」に認証され、バッグは京都ギフトショーで大賞を受賞し注目を集めている。

取引先のお皿がほしいというニーズに応えた「花組子®プレート」。

吉野檜とウォールナットの2色から選べる「花組子®」シリーズのペンダントライトと、組子細工と鞄職人とのコラボーレーションで生まれた「花組子®バッグ」
「以前、腕のよい職人さんが作られた七宝組子を拝見することがあり、『いつか自分でも製作したい』と思っていました。そんな時、おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金の公募を知り『縁がつながる』という七宝組子の意味にちなんで人々を笑顔にするものを作ろうと動き出しました」。

木を細くカットして部材を加工し、手で組んでいく。0.05mmのずれで組み付けが合わなくなるため、精巧な技術を要する。
「imadoco」でコラボしたデザイナーのナカジマミカ氏に依頼したところ、組子をできるだけ薄くしてほしいと要望があった。通常組子の厚みは10㎜前後のところ、精巧な技術により3㎜の薄さを実現。ライトの組子は木枠をなくしてレースのような繊細さを表現するため、アクリル板に貼りつけ強度を担保した。バッグは貞子氏が「使いやすいよう上質な革と組み合わせたい」と鞄の縫製会社を探した。食器を手がけるのも初めてで、塗料探しなど挑戦の連続だった。「デザイナーとの協働は固定観念を覆されることもあるが、柔軟な考えが大事だと思った。職人とデザイナーとの調整や商品企画では妻に苦労を掛けたが、納得のいく仕上がりになりました」と種村氏。

階段箪笥を現代的なモダン家具に提案した「HACO-DANCE」(左)と、大切なものを飾る床の間を創る家具「imadoco」(右)。
大量生産ができないため卸売りはせず、百貨店の展示会やネットショップで販売。フランスの展示会に出品したが、関税や送料で高額になるため国内に注力することにした。HPから工務店やハウスメーカー、建築事務所のほか、一般の方からの問い合わせも増えている。「新商品がきっかけで本業の宣伝になり、建具の受注につながっている。製作・販売・企画のバランスを取るのが難しいが、本業を大切にしながら、丁寧な仕事を届けていきたい」。今後は世界無形文化遺産である建具の技術を絶やさないために、職人育成にも力を入れていく。

(取材・文/三枝ゆり 写真/福永浩二)