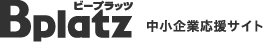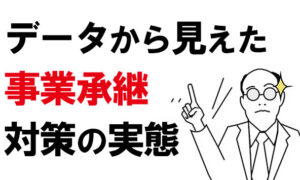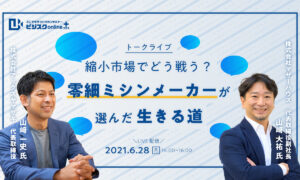《講演録》家業の枠を超え未来を創る!先駆者から学ぶ「家業」と「新規事業」を両立させる秘訣

2025年3月12日(水)開催
【若手後継者のための勉強会】家業の枠を超え未来を創る!先駆者から学ぶ「家業」と「新規事業」を両立させる秘訣
講師 小西 康晴氏
(生野金属株式会社 代表取締役/株式会社ロボリューション 代表取締役/一般社団法人i-RooBO Network Forum会長)
今回の講師は、1947年創業の金属製缶の製造・販売を行う生野金属株式会社3代目、小西 康晴氏。2005年に家業である同社に入社し、組織づくりや製造工程の改善に取り組みながら、事業承継に向けた準備を進めてきた。同時に、自身の関心が高かった「ロボットビジネス」に注力するため、2006年に株式会社ロボリューションを設立。家業と新会社の連携を図り、シナジー効果を生み出す経営を実現している。現在も、家業を守りながら独自の事業を展開し続ける小西氏が、家業にどう向き合い、やりたいことを実現してきたのか。本セミナーでは、小西氏の体験をもとに「組織づくり」「新規事業との両立」をテーマにお話しいただいた。
目次
■ ソニーの「aibo」に感動して
生野金属は祖父が創業し、私自身は後継ぎという立場でしたが、幼少のころは建築士になることが夢でした。小学校の遠足で橋の建設現場を見学し、自分の作品を社会に残すような仕事をしたいと思うようになったのがきっかけです。
大学生のころ、ソニーがペットロボット「aibo」を発売しました。電源を入れてaiboが動きだした瞬間、その姿に感動し、「ロボットは次世代の産業になる」と確信しました。そこから建築とロボットの両方の研究に取り組むようになりました。
大学院卒業後は村田製作所に入社し、最先端の製造生産技術を用いたメカトロニクス機器開発に携わり、メカ設計などを行いました。ちょうど同社は新プロジェクトの立ち上げ期で、自ら設計・制作・組み立て、そして広報体制の構築にも携わり、さらに地方拠点で製造ラインの立ち上げと量産開始までを経験しました。この知見は家業にも活かすことができると感じ、入社から3年後に家業である生野金属に戻ることにしました。
■ 「0→1」でロボットを実用化
生野金属では生産技術部に配属されましたが、すぐに村田製作所との大きなギャップに直面しました。最先端の生産技術や自動化、効率化が進んでいた前職とはかけ離れた、1工程ずつに人が配置される現場だったのです。
一方、入社1か月ほどして大阪・梅田の北ヤードに、ロボット関連のスタートアップや研究者向けのコワーキングスペース「ロボシティ・コア」ができるという新聞記事を目にしました。そのころ、大阪産業創造館でロボットビジネスの起業を支援する塾があり、1期生に選んでいただきました。それから1年をかけ、2006年6月に株式会社ロボリューションを設立しました。
ロボリューションは、いわゆる産業用ではないロボットの開発・導入をプロデュースする会社です。クライアントは関西に本社がある大手企業が中心で、ロボットの新規事業を立ち上げたいけれど自社に技術や人材が足りない場合などに、弊社が“まとめ役”になるのです。
実績としては、前職の村田製作所との一輪車ロボットの開発担当や、大和ハウス工業と遠隔操縦で床下点検ができるロボットを開発しました。このほかに、エレキバンやスリムウォークを展開するピップから依頼を受け、独居高齢者を対象にメンタルケアを行うロボット「うなずきかぼちゃん」を開発し、こちらは1万8千体を販売しました。
こうした「0→1(ゼロイチ)」でロボットを実用化していくことこそが、ロボリューションの使命です。ロボットを使って差別化を図りたい大手企業をはじめ、センサやアクチュエーターの製作を自動化したい要素技術メーカーとの架け橋になり、アッセンブルする製造業者とコンソーシアムを組んでロボットとして納品し、サービスを作り上げていくのが特長です。
■ ロボットと既存サービスを掛け合わせ
「餅は餅屋」といいますか、私は開発において、その道のプロを巻き込んで新たな価値づくりをしたほうがより新しく面白いものができると思っています。ロボリューションのモビリティ事業ではそれを体現しています。
チームROBOLUTIONでロボット技術者は自社を含め3社のみ。そのほかは一級建築士、ゲームサウンドクリエイター、プロダクトやウェブデザイナー、造形作家などです。そうしたメンバーで現在8種類のモビリティを展開しています。
大阪・関西万博のプレイベント「花園EXPO」の期間中には、自律型ロボットモビリティを活用し、身近なものとして受け入れてもらえるよう繰り返しデモンストレーションを行いました。またシンガポールのチャンギ空港でも、これまで1人1台で押していた車いすでの移動サポート業務を、追従機能を持ったモビリティを導入することで、1人が3台まで連ねて広い空港内を移動できるようになりました。こうして、既存のサービスや機器と掛け合わせることで、いままで動いてなかったものを動かすことができるようになっています。

■ 三品産業がメインの缶作り
生野金属では、缶を製造しています。18リットル缶からお菓子の缶、塗料の缶、スパイスの缶など、皆さんのご自宅にも、うちの缶が一つはあるのではないでしょうか。デパ地下のお菓子の缶や蚊取り線香の缶なども含め、年間で1,200万個の缶を作っています。
当社の特徴は、食品関連の缶が多いことです。「品質基準の厳しいものほど引き受ける」という方向性を定め、営業メンバーが動くと、食品、医薬品、化粧品といった分野の注文がどんどん増えてきました。いわゆる「三品産業」をメインに缶づくりをしています。
直近7期の売上げでいうと、71期ではコロナ禍の影響で売上げが2割ほど減りました。さらに、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で材料も高騰し、72期は営業利益で8,000万円の赤字でした。しかし、今では新規事業の取り組みが花を咲かせ、直近の75期までは増収増益、76期はコロナ禍前の売上げを超えて、27億円まで到達できそうな見込みです。
■ 5S活動とM&A
私が社長になってからの取り組みを共有したいと思います。品質基準の厳しい缶づくりに舵を切ると、上の人は「5S活動を頑張れ」といいがちです。いわゆる「整理(Seiri)」「整頓(Seiton)」「清掃(Seisou)」「清潔(Seiketsu)」「躾(Shitsuke)」ですね。しかし予算もなければ、めざすべき指標が現場のメンバーに示されるわけでもない。
調べたところ、食品安全マネジメントシステムに関する国際規格「FSSC22000」があると知り、その認証を取得することを全社的なプロジェクトに位置付け、私自身が食品安全チームリーダーとなって取り組みました。
工場の部品や棚の整理整頓には事務所のメンバーも一緒に行いました。社員全員が5S活動に携わることで事情も見えてくるし、私自身もメンバーと工場内でいろいろ話せるようになりました。2015年に認証を取得したのですが、その後に食品メーカーが見学に来られ、営業活動におけるコミュニケーションのツールにもなっています。
■ デザイン経営との出合い
コロナ禍に、ある会社をM&Aしたのですが、その最中に「デザイン経営」という言葉に出会いました。これは、企業が未来のありたい姿や社会的存在意義を見定めたうえで、デザインの力を経営に活用し、ブランド力、イノベーション力を高め、企業競争力を向上させる経営手法です。デザインによる経営プロジェクトに参加したことで、私自身や自社の棚卸しができたように思います。
その中で、弊社では「さまざまな平面を美しい立体にして届ける」というミッションを掲げました。缶はすべて薄板の大判1枚から、折り曲げたりプレスしたり溶接したりして容器にしています。昔はその技術を使って大手メーカーの電子レンジのフレーム制作や、新しい分野へのチャレンジを行っていましたが、鋼材価格の高騰や缶から箱への置き換わりなど、自分たちが求められる場所が減る中で、必要なのは新しい定義づけだと思ったからです。
弊社は「0→1」が得意な会社ですが、「届ける」という部分が弱いという課題がありました。そこで、社内の若手女性メンバーを中心に「01A PROJECT」を立ち上げました。手のひらサイズの「コロン缶」をテーマに、「1をA」にするためのプロジェクトをスタートさせました。この活動の中で、生産現場にいた女性がチームリーダーとなり、一昨年からは社員として登用されました。頑張れば評価されるというのが一つ示せたことで、特に若いパートさんたちの仕事への取り組み方が目に見えて変わっていきました。
■ 新たな価値を「接ぐ」
「つぐ」という言葉に漢字を当てると、「継ぐ」と「接ぐ」があります。私がいま大事にしているのは「接ぐ」であり、それは「接木」のイメージです。接木は育ちの遅い品種や環境に弱い品種の枝を切って強い品種に接ぐことで健全に育成させるという目的と、良い花や実をつける樹木の優良な性質を損なうことなく増やしていく目的があります。
親世代からは「木に竹を接ぐようなもの」と批判されるかもしれません。しかし、私の解釈としては、木に竹を接ぐのは「新たな価値創出にチャレンジする」ことだと考えています。一歩踏み出すと、後からいろいろなことがついてきます。何も進まないよりは、まずは社内を巻き込んで一度やってみる。それがいかに大事かを、私はこれまでの経験から学んできました。
この「接ぐ」という行為は、後継者である皆さんにしかできないことです。皆さんが持っているもの、考えていること、これから作っていくものをどうアレンジしていくかが、これからの会社の未来を楽しくしていくポイントだと思います。
(文/安藤智郎)
 小西 康晴(こにし やすはる)氏(生野金属株式会社 代表取締役/株式会社ロボリューション 代表取締役/一般社団法人i-RooBO Network Forum 会長)
小西 康晴(こにし やすはる)氏(生野金属株式会社 代表取締役/株式会社ロボリューション 代表取締役/一般社団法人i-RooBO Network Forum 会長)
2002年、慶応義塾大学大学院理工学研究科空間環境デザイン専修修了。株式会社村田製作所に入社。2005年退社し、父が経営する生野金属株式会社に入社(現在、代表取締役)。2006年6月、サービスロボットの開発・導入コンサルティング事業を行う株式会社ロボリューションを設立。RTビジネスプロデューサ/RTシステムデザイナーとして、各種開発プロジェクトに参画。以降、大手企業の新規ロボット事業プロデュースにおいて、多くの実績がある。現在は、事業承継をテーマにしたセミナーや起業家育成プログラムのメンターを担当するなど、多方面で活躍中。