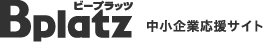先代の遺産生かし、面白いものづくりに徹する

2級建築士の資格を持ち、施主の思いを引き出しながら設計、デザインの仕事に落とし込むリフォームの仕事に携わっていた川口氏。個人向けにバッグ用生地を販売する店を営む父が余命宣告を受けたのは、社会人になって10年が経った頃だった。
事業承継のことなどまるで念頭になかった川口氏だったが「父が築いてきたものをなくしてしまうのはもったいない」と入社を決めた。直後、安心したかのようにすぐに息を引き取った。事業の引継ぎはできなかったが、先代は「仕事はこれからますます厳しくなる」とただひとことだけ言った。

右も左もわからない中で、仕事のイロハを教えてくれたのは仕入先の生地メーカーだった。「質の良いものを提供するには質の良い生地からと父は考えていたようで、仕入先を大切にしていたからこそ」と先代の遺産に感謝する。ただ、売り先は60代以上の人が多くを占め、放っておけば顧客が減ることは火を見るより明らかだった。
川口氏はバッグに関する知識を学ぶためバッグづくりの教室に通い、そこで得た素材や資材の知識を基に仕入先と、売り先双方に対して提案の引き出しを増やし、扱う生地のバリエーションを広げていった。


「他社と似たようなものを売っていては面白くない」。そう考えた川口氏は4年前、東京の生地展示会に初めて出展。自らデザインしたユニークなデザインの生地を並べた。
自社が最も得意とする熱加工。この加工技術はエンボスでは表現できない深い陰影が浮かび上がり、より一層デザイン性が高くなった生地は、海外のアパレルハイブランドの目に留まり注文が舞い込んだ。また海外向けに新しいシーツの素材を考えてほしいと依頼があった商社に対しては、富士山の溶岩の粉末を練り込んだ糸と、銀を表面に塗布した糸を織った生地を提案。日本らしさを表現し抗菌という機能性も加えた。バッグにとどまらず生地の顧客はどんどん広がっている。

昨年夏、新たに輪転プレス機を導入した。いったん紙にプリントしたデザインを高温高圧で生地に転写することで直接インクを生地に吹き付けるより、色鮮やかに線もくっきり印刷できる。
「コロナ禍で、個人の趣向がより細分化し、小ロット多品種のものづくりが今後より求められるようになる」との判断から、内製化を決断。今まではコスト面で大きなロットでしか対応が難しかったが、小ロットの注文も受けやすくなった。さっそくファッション専門学校の卒業制作に使う生地の注文が舞い込んでいるという。

また、今年はパーテーション生地など空間演出用の提案も始める。
「目先の利益よりも、だれかに、社会に役立つことで価値を高めていきたい」と長期的な視野で事業展開を考えている。

代表取締役 川口 健一郎氏
(取材・文/山口裕史 写真/福永浩二)