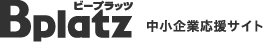オールリセットからの17年、人を生かし、お金を生かす

河内エリアは、ワインの副産物である酒石が軍事利用された時代に国策としてブドウ畑が整備され、一時は日本有数の栽培面積を誇った。
同社は戦後、大手酒類メーカーにワインを売るOEM生産で安定した事業を営んできたが、順調だったのは1990年代初頭まで。バブル経済が破綻して嗜好品の消費は一気に縮み、頼みの綱だった大手酒類メーカーからの製造受託もなくなっていった。


経営に逆風が吹き始めた頃に先代が急逝する不幸に見舞われた。当時20歳だった金銅氏が大学卒業後、酒類卸会社に3年間勤め家業に戻ってきたのは2005年のことだ。多額の借金を前に出した答えは「オールリセット」。50種類ほどあったワインの全量を引き取り、取引先もゼロから見直す一方、ゼロから自社ブランド商品を立ち上げた。
ターゲットに据えたのは「ライトユーザー」。ワインだけでなくスパークリングワイン、リキュールなど入門者にも受け入れられやすい商品をそろえた。「口を出す先代がおらず、過去のしがらみがなかったことで大胆にやりたいことができた」と逆境をむしろ前向きにとらえた。

代表取締役社長 金銅 重行氏
「外に売りに行くだけでなく、いかにお金を運んできてもらえるか」を考え、ワイナリーに客を呼び込む仕掛けに注力した。そこで生きたのが、先代が亡くなる間際、いずれ直売場にと建てた「河内ワイン館」だ。「ライトユーザーは味以上にいかに楽しめるかを求めてやってくる」と考え、社員、パートによるガイドの充実を図った。各人の個性を生かした案内が人気を呼んだ。見学予約時にガイドを選べるようにし、人気度で報酬もランクづけされ、ガイドのモチベーションになっている。
「河内ワイン館」を拠点にめざすのは「道の駅のような場」。周辺農家が生産するブドウをはじめとした物産を売るなど「地域が築いてきた歴史を守る」ことで共存共栄をめざす。近隣の農家の繁忙期には社員の派遣まで行っているという。

直売場「河内ワイン館」
コロナ禍は、再建過程で知らず知らずのうちにたまってきた澱を除く良い機会になったという。観光バスもむやみに受け入れることをやめ有料化に切り替えた。「お金を払ってくれるお客さんにより喜んでもらう仕掛けが大事」。それが社員の士気にもつながる。従業員の働き方についても年中週休2日の働き方から、繁忙期は詰めて働いてもらう一方、閑散期の1、2月は1カ月くらい休めるよう改めようとしている。「その間に南半球のワイナリーに研修に行ってもらってもいい」。
家業に戻ってきてから17年間、生きたお金と時間の使い方を常に追求してきた金銅氏。「当初60点をめざしてきたワインの質も80、90点をめざすレベルになってきた」と手応えを感じている。

「父は人を引き付ける魅力を持った人だった」と在りし日の父を思い起こし、「人をあきさせないことが商いとも言っていた」と思いをはせる。
河内ワインを生んだ歴史と地域で築いてきた信頼を生かしながら顧客、従業員、そして地域のことを考え、金銅氏は今日も新たなチャレンジを続ける。

(取材・文/山口裕史 写真/福永浩二)