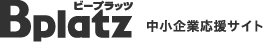“日本流”を輸出し カンボジア農業に貢献

自力での国際支援をめざし起業を決意
東南アジア諸国に日本産の農産物を輸出・販売する「Made in Japan」と、カンボジアの農場で日本流の栽培ノウハウを使って生産・販売する「Made by Japan」で日本の農業の可能性に挑む。
前者ではカンボジア、タイ、マレーシアにカキ、イチゴ、ブドウといった果物を輸出。後者では現地の農場でオクラ、キュウリ、トマト、レタスなど約20種類の無農薬野菜を生産し、プノンペン市内の大手スーパーやレストランに卸している。
現地での農地の確保から流通システムの整備まですべて自力で手がけた。「僕たちが日本の農業の新しい海外展開のモデルを確立し、後に続く人をつくろうと思った。だからつぶすわけにはいかなかった」と、阿古氏は黒字化を果たすまでの3年の道のりを振り返る。
もともと開発途上国の支援にかかわる機関で働く国際公務員をめざしていた阿古氏。そうした機関では現地の求める課題に即した支援は難しいと知り、気持ちが薄れるが、自身で稼いだ資金で独自の途上国支援を行う起業家と出会い、「いつか自分も」と再び心に火がついた。
いったん人材業界に就職し、独立に向けた準備を進めていた矢先、農業資材販売業を営む父親から事業を手伝ってほしいと連絡が入る。初めて触れた農業の世界には将来の希望を見出すことは難しかった。「ただ、これから経済成長するアジア諸国に機会を求めればチャンスは広がる。日本の安全な農作物は求められるはず」。意気投合した農業生産者たちとともに会社を設立した。
当初は中国市場をターゲットに定めたが、カンボジアの農場を視察して考えが変わる。人口の8割が農業に従事する国。生産性が低いために、子ども達が労働力にならざるを得ず、学校に通えない実態を知った。
「カンボジアの国民性を反映して圃場づくりは丁寧で、地域によっては粗悪な農薬もほとんど使われていない。そこに日本の農業技術を融合させれば安全な農産物の生産性が向上する。ひいては子ども達が学校に通えるようになる」。事業そのものが途上国支援につながる理想のビジネスモデルに行き着いた。

ライフワークだからこそ続けられた
カンボジアでの農場探しから始まった。自身の思いを伝えて歩くうち、無償で貸してくれる農園主と出会った。農園の確保と同時に2012年に現地法人を設立。栽培に適した野菜は何か、通年で生産できるか、どのような病害虫がつき、どのように防除できるのかを1年半かけて研究した。
安定収穫できるめどが立ったものの、新鮮なまま店まで届けるシステムがないことに気づく。プノンペンの市街地に配送センターを確保し、野菜をパッケージし、配送する体制を整えた。
並行して、日本からの果物の輸出も手探りで始めた。現地の展示会に出してわかったことは、硬いものが好まれ、日本のように熟した果物の食感が敬遠されること。すぐさま日本の共同経営者の農家に電話を入れ、収穫を前倒しにするように依頼した。
「難しいのは売れる商品をどうやって届けるかということ。私たちの場合、農家と直接のネットワークも多岐に渡り、求められる農産品をすぐに開発できるし、他の商社を通さないため物流にかかる時間もコストも抑えられる」と強みを挙げる。
何もかもが手探りの中で壁にぶつかりながらもがいてきた。カンボジアで朝の8時から真夜中の2時まで働く日が100日以上続いた。出資金は底をつき、個人の借り入れでしのいだ。それでも続けられたのは、「この仕事こそ自分のライフワーク」と思えたからだ。
だが体は悲鳴をあげていた。ある夜に倒れ、緊急搬送された。妻は身ごもっていた。「僕が壊れたら、家族にも周囲にも迷惑がかかる」。そう考えた阿古氏は、カンボジアに戻って「現場の仕事は一切やらない、マネジメントに徹する」と宣言した。
現場でミスが発生しても、自分が解決に奔走するのではなく、すべて現場のカンボジア人スタッフにその理由を考えさせ、対策をとらせた。これが現地のマネージャーのモチベーションを刺激し、徐々に任せても仕事が回るようになっていった。「今では年間のシフト調整も含めすべて任せ、何が起きても解決できるようになった」。創業から3年かかってようやく黒字化にこぎつけた。

日本の農業モデルをカンボジア全土に
現在、農場は提携農場も含め、約10ha規模に達している。阿古氏は現地で農業指導するにつれ、日本が長年築き上げてきた農業技術、インフラの優位性をつくづく実感している。防除技術もその一つ。防除には農薬を使う化学的防除、農業従事者の手入れによる耕種的防除、資材を使う物理的防除、天敵などを使う生物的防除の4つがあるが、日本の農業にはこれらを巧みに組み合わせる技術が成熟しているという。
さらに、「産業」に育てたのは流通・金融を含めた農業インフラだ。「全国どこでも安全な農作物を常に供給できる仕組み。これが日本の農業の最大の強みであり、それを可能にしたのがJA(農協)と農政」と指摘する。栽培技術は国の機関が研究し、農協は栽培指導から、農産物の販売、生産インフラ投資のための金融まで整える。
阿古氏が実現をめざすのは「カンボジアの農協」だ。栽培方法だけが「Made by Japan」ではない。農業をカンボジアの一大産業にするための仕組みを「Made by Japan」でつくろうとしているのだ。
今後は提携農場をカンボジア全土に拡大していくとともに、近隣諸国への輸出もにらむ。すべては自身が掲げたミッションを遂行するため。阿古氏のカンボジアでの挑戦はまだまだ終わらない。
(取材・文/山口裕史)
株式会社ジャパン・ファームプロダクツ(カンボジア)
代表取締役社長
阿古 哲史氏
資本金/10,000ドル 従業員数/26名 設立/2012年
事業内容/野菜・果物の現地生産及び提携生産、日本の農産物及び加工品と現地生産野菜の販売、農産加工品の開発。