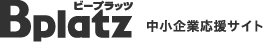国内に2社のみ 手積みの技術を継承する国産坩堝メーカー
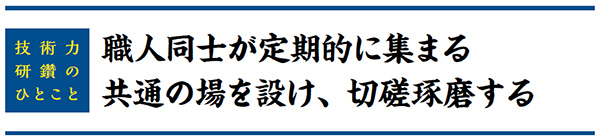
「鋳る壺」が語源とされる「坩堝(るつぼ)」。飛鳥遺跡でガラス装飾品とともに出土されるなど、古くからガラス職人らの手によって使われてきた“工業炉”だが、今や国内でこの坩堝を造っているメーカーは大阪に2社を残すのみ。そのうちの1社が奥村坩堝製造所だ。「かつて大阪だけで坩堝メーカーは8社ほどあったが、小中規模のガラスメーカーが淘汰されるにつれ減っていってしまった」と多田氏は言う。

現在造っている坩堝のうち7割は地酒や焼酎用の特殊な手吹きガラス瓶や電子部材フリットおよび特殊ガラスの製造用をはじめとする大型坩堝で、残りは全国のガラス工房から注文を受ける小型坩堝だという。「坩堝はガラスを溶融するための窯の中で1350度もの高熱で繰り返し使われるので、寿命は長くて2~3カ月ほど。その苛酷な環境でいかに安定して長持ちする坩堝を作れるかが腕の見せどころ」と話す。
坩堝は、まず蝋石とシャモットと粘土を混ぜ合わせたうえで1ヵ月寝かせる。その後、この杯土を使って10日ほどかけて手作業でつぼ状に成型し、いったん2週間ほど乾燥させてから、炉で10日間ほどかけて焼いて完成する。
海外製の坩堝に比べ、品質が高いことで知られる同社の坩堝の強みは、一見したところ、土を使ってつぼ状に成型していくという点では陶芸と似ているが、耐火度が必要な坩堝に使われる土は粒子が荒く、成型が難しい。
また、坩堝の種類によって15~30mmと異なる厚みやカーブを手の感覚だけに頼って調整する。そのため、この加減を誤ればひびが生じやすく割れてしまうという。
多田氏は8年前、前社長から請われ、取引先であるガラスメーカーから転身した。「この会社に来てまず感じたことは、の高齢化でした」と、高校や派遣会社を回って若手の職人を採用。「辞めずに続くのは10人に1人」という中から、4、5人の若手の職人が育ち始め、かつて55歳ほどだった職人の平均年齢が今では10歳ほど若返った。
近年はガラス用の坩堝に加え、金属溶解用、さらにはインド料理のナンを焼くための窯へと製品の幅を広げている。
坩堝とその派生品の製造に加え、現在、多田氏が力を注ぐのが、「坩堝や特殊な溶解炉を使った精密ガラス部品やセラミック材料の開発」だ。坩堝の製造技術に加え、多田氏がガラスメーカー勤務時代に培った各種ガラス製品製造のノウハウを組み合わせ、新商品の開発に挑む日々。本社敷地に新たに設けた研究所では2人の女性社員が、温度変化がガラスの組成に与える影響などの研究に没頭し、新製品開発の種を育てている。

ろくろを使った成型作業。若手の職人が育っている。

時間をかけて手積みで成型していく。

研究室では入社間もない女性社員が活躍している。
(取材・文/山口裕史)
株式会社奥村坩堝製造所
代表取締役社長
多田 嘉宏氏
http://www.okumurarutubo.co.jp/
職人1912(大正元)年の創業。耐火煉瓦の製造でスタートし、その後坩堝の製造も始めた。現在は全売上げのうち、坩堝が25%、レンガ製品などの
加工品が25%、ガラス溶融が20%、各種耐火物の卸が30%を占める。