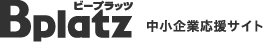立ちはだかる「両親」の存在乗り越え、真の経営者に

3人目の子どもが1歳を迎えたころ、礒部氏は大きな決断を迫られていた。両親が営む段ボール工場に特化した排水処理設備の会社を継ぐか否か。「専業主婦を大いに楽しむ」はずの人生計画が狂いだしたのは、事業を継ぐはずの弟が会社から飛び出したからだった。
「社員を路頭に迷わせるわけにはいかない」と覚悟を決めた。夫が快く送り出してくれたことが救いだった。
社長だった父はいわゆるワンマンタイプ。命令口調で全て自分が一番。対立構造にあった父と社員の間を礒部氏が“翻訳”し間を取り持つことから仕事は始まった。
だが父は経営の決定権を一手に握り、経理を担当していた母は“財布”を手放さない。会社のホームページ一つ作るのでも「売り上げが増えるわけでもなし」と反対する父をやっと説き伏せたかと思えば、母が出費を渋る。鉛筆一本を買うのにも困難を極め、「一事が万事、そんな調子でした」。

そして入社7年が経った2013年、礒部氏がいよいよ社長に就任する。だが「私を会社のマスコットのようにしか思っていなかった」父に経営権を手放す気配はない。
とはいえ、社員も取引先も礒部氏に向き始めていた。「このまま何もできないのでは恥ずかしい」と、無料の経営セミナーに片っ端から通いつめ、「理詰め」で説得し、就業規則を作り残業手当を支給するようにした。
営業も設備も父が担当していたが、営業担当の社員や、設備設計の担当者が一人また一人と礒部氏の良き相談相手になり、そこを突破口に営業、技術開発の手掛かりを見つけていった。
だが肝心の融資は母の担当だ。ある日、母の不在時に新規営業に来た金融機関の担当者と話すようになり、そこから融資を得ることができた。それまで母と通じていた別の金融機関の担当者が今までよりいい条件の融資を提案、礒部氏に歩み寄ってきた。
そこから、仕事がやりづらくなくなった母が3年前に辞め、あとを追うように父もその1年後に会社を離れた。

代表取締役 礒部薫氏
晴れて重しは取れたが、「共通の敵がいたからこそまとまっていた社員との一体感は薄れてしまった」と苦笑する。
「今こそ会社としての本質が問われている」とめざすのが「人格経営」だ。「社員の子どもさんのことまで考えると、今いる社員が欠けることなく、少しでも給料が上がるようにしていきたい。そのためにはまず人間力から育てていかないと」と考え、あいさつの徹底、相互扶助の大切さを説く。
一方、事業面では昨年、排水用フィルターのメンテナンスサービスを新たに始め、軌道に乗せつつある。

両親、弟とはぎこちない関係となったが、社員を思う気持ちで信念を貫いてきた。そして「すべてを肯定してくれた」夫への感謝の念も忘れない。
「自分のように普通の主婦でいた同年代の女性にも一歩踏み出してほしい。まさかまた仕事をするなんて思いもしなかった私でもやってこれたのだから」と礒部氏。
14年前、跡を継ぐか悩みに悩みぬいたあの頃の自分にはこんな言葉をかけてあげたいと言う。「なんとかなるもんだよ」と。

(取材・文/山口裕史 写真/福永浩二)