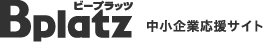やってみなわからん、 あかんかったら次。

滋賀県米原市にある本社の周囲にはのどかな田園風景が広がる。眼前にそびえる伊吹山が湛える水は古来この地に豊かな恵みをもたらしてきた。かつて盛んだった養蚕業もその一つ。北近江一帯は繭からつくる真綿布団の産地としても知られる。
横田氏の祖父はその真綿布団の縫製加工から会社を育て上げた。2代目の父は1980年代後半にシュラフ(寝袋)製造へと転じる。そして、3代目の横田氏は新たにアパレル事業に挑み、国内で精製したダウンを使った高品質のシュラフ・ウエアメーカーとしてコアなアウトドア愛好者の支持を集めている。
横田氏の最初の就職先は貸衣装屋、営業職だった。「幼いころから長男らしく育てられたので、継がなあかんのやろなと。最初から家業に役に立つ仕事をしようと思ってました。職人あがりの父の商売は営業力が弱いことはわかっていたので」。

のどかな田園風景が広がる本社周辺。奥にそびえるのは伊吹山。
3年後、「お前1人を雇う余力はできた」と父に言われ、入社した。初任給は15万円。出社初日に父から「明日から回ってこい」と全国の店舗リストを渡され、300万円分のシュラフを車に積んで出た。「何しに来た」と店の人にどやされながらも、他社製にはない強みを教えてくれる人もあり、そのまま売り文句にした。「父はやってみろと言うだけであとはほったらかし。10人いる社員の給料分を稼ぐためにどう売ったらいいかを必死で考えた」。
父自身「まずはやってみる」の精神で生き抜いてきたことを横田氏は知っている。シュラフに打って出た時には保温機能を高めるために手間のかかる縫い方にこだわり、1日1本しか縫えない時がしばらく続いた。永久保証も付けた。唯一の国産シュラフメーカーとして、国内に工場を持ち、迅速に対応できる強みを生かそうと考えたのだ。
シュラフをつくり始めてからも常に同じところにとどまることはなかった。あるときは棺桶用の寝袋をつくった。「これは結局在庫の山に代わって、最後は100円で売り払いました。魚屋さんに合羽を売りに行ったこともある。やってみなわからん、あかんかったら次、で進んできた」。

OEMでウエアをつくってほしいという話が横田氏のもとに舞い込んできたのは25歳の時のことだ。元々アパレルには興味があった。何よりシュラフに使うミシンをそのまま使うことができる。初年度にダウンのベスト、ジャケットを300枚ずつつくった。だが結果は赤字。原価を抑えるために梱包資材から見直しを図った。
「親父にはむちゃくちゃ怒られましたが、息子やからそれでも続けられた。自分で選んで入った世界ですから。わからないことは外の人を頼って聞いて。20代だから許されたんでしょうね」。

社長を継いだのは32歳の時。父が唯一手放さなかったお金の管理も見られるようになり「自分がやりたい投資ができるようになった」。徐々にウエアの売上比率が増え、現在ではウエアが7割、残りをシュラフが占める。シュラフと同じようにウエアについてもOEMから始まった生産を「NANGA」ブランドへと切り替えていくことが大きなテーマだ。
「厳しい目を持っている人にNANGAの製品はいいよと思ってもらうことが一番。そうすればおのずと広がっていきますから」。売上げを追うことはしないが今のままでよしとはしていない。「今の価格では縫製工の給料を上げられない。いいものを作っているという誇りと自信を持って働き続けたいと思ってもらうことができなければ未来はありません」。そのためには生産性を上げることはもちろん、ブランド力を高めることこそ重要と横田氏は説く。

視野に入れるのが海外市場だ。世界で目の肥えた人に評価されれば国内でもおのずと価値が上がる。「この地でやり続けていくためには失敗はできない」。今年は新たに米原市内に物流倉庫も完成させる予定だ。
ある時、結婚を考えているという社員から「ナンガで働いていると言って彼女の父親に反対されないか心配だ」と言われ、ガツンとこたえた。「世間から見ればまだまだ無名の会社。社員が堂々と胸を張っていられる会社にしないと」と誓う。しんどいこともあったが、継いでよかったと今、心から思える。「どんな家業でも知れば知るほど面白くなる。その仕事が成り立っているということは面白くないわけがない」。
今、弟の敬三氏にシュラフの事業は委ね、ウエア事業に専念する。米原の地で、「従業員一人ひとりの夢が会社の夢になるような会社」をめざし、今日もダウンの道を究める。

代表取締役社長 横田 智之氏
(取材/山野千枝 文/山口裕史 写真/福永浩二)
★アンケートやってます★ぜひご協力ください★
https://www.sansokan.jp/enquete/?H_ENQ_NO=22863
☆2月号「ベンチャー型事業承継」特集はコチラから☆
https://bplatz.sansokan.jp/archives/category/201702