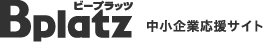100%業態転換した今も原点は父の言葉

「鈴木商店」。社名はいかにも古風だが手がける事業は最先端だ。西天満のオフィスビルの本社フロアを埋めるのは35人のエンジニア集団。
クラウドコンピューティングを活用した大手出版社向けのダウンロード販売システム、建材メーカー向けの現場報告書作成システムなど数々の実績を積み重ね、成長を続ける。そこに先代の父親から引き継いだ印刷資材卸販売業の面影はかけらもない。
会社を継ぐことに迷いがなかった鈴木氏ゆえの決断と、父親が築き上げた目に見えない資産があいまってこそ成し遂げた換骨奪胎だ。
先代の体調がすぐれなかったため、学生の頃から家業を手伝わされた。零細な印刷工場にインクを届けては御用聞きをする繰り返し。遊びたい盛りゆえ気乗りはしなかった。
あるとき配送に使っていたトラックのダッシュボードの中に大人用のおむつを見つけた。大腸がんをわずらいながら働く父を思い、スイッチが入った。幼い時父に仕事場に連れられて刷り込まれた「印刷屋の怖いおっちゃん」を相手にひるむばかりだったが、「断られたところで損はない」と諭す父の言葉を思い出し、前へ出ることを覚えた。

鈴木氏にとって継ぐことは当たり前だった。大学卒業後も配達業務を続けたが「誰が届けたところで同じインク。儲かる気配はゼロだった」。
突破口を見出したいと考えた鈴木氏はある日、「東京のシステム開発会社で勉強させてほしい」と父に頼み込む。I T 革命と騒がれていた頃。システムを勉強しておけば何か会社に生かせるのではと考えたのだ。「父の容体がいつ急変するかわからない。いつ呼び戻されてもいいように吸収できるものはすべて持ち帰ろうと毎日誰よりも遅くまで残って仕事をした」。

結局4年半勤務した後、30歳手前で会社に戻った。再び配達の仕事が始まった。16時まで働いて月給は8万円。残りの時間で勉強の成果を生かそうとシステムやインターネット関連の仕事を始めた。幼い頃から知る印刷屋の社長が「ぼんががんばってんのやったら応援したるわ」とショッピングサイト開設やシステム構築の仕事を紹介料なしに次々につないでくれた。
手が足りなくなった分は、旧友に声をかけシステムのイロハを教えながら夜中まで開発を手伝ってもらった。「父親が築いた家業の信頼や人脈があったこと。そして家業のキャッシュが毎月小規模ながらでも回っていたからITの仕事を細々と副業として始めることができた」と振り返る。

その後、徐々にシステム開発の仕事が軌道に乗り始め、本業の仕事を凌駕するようになっていく。そして2010年、父が他界。元気なうちは手放せなかった印刷資材の商売は、父親の後輩に譲ってきれいに畳んだ。
父の背中を見て幼心にも、会社経営には浮き沈みがあることを肌身で感じていた。「小さい頃はうちは裕福やと思ってたんですが、知らない間に親父が僕の保険を解約してたり(笑)。ああ、そうやって会社のお金をまわしてたんやなぁと」。
いまめざすのは「短期的な利益を追い求めるのではなく、骨太の組織力で勝負できる」開発会社だ。「エンジニアは全員正社員」にこだわっているのも、一人一人を育成し、互いの信頼関係を醸成することに時間と熱量をかけるんだという鈴木氏の覚悟の現れでもある。「簡単に積み上げたレンガは簡単に崩れる。時間やお金がかかっても長い目で見ればこっちのほうが会社のためになる」。

とはいえ強い組織は簡単には生まれない。数年前に仕事の受注量が増えたことに合わせ、エンジニアの採用を一気に増やした。気づけば35人いる半数以上を1年以内に入社した社員が占めていた。教育が行き届かず、発注先とのトラブルが続いた。その反省をふまえ、間接部門の人員を厚めにすることによってエンジニアの負担を減らし、開発に集中できる環境を整えつつある。
「今期は足場固めの時期。近視眼的に利益を狙うことはせず、来期以降の飛躍につなげていきたい」ともくろむ。今思えば、息子の弱点をよく知る父が数々のアドバイスをしてくれていた。「おまえはすぐ油断する、とよく言われました(笑)。また調子に乗ってるかなと、今でも父の言葉で自身を戒める時がある」。

幼いころ父が自分にしたように、週末は6歳の息子を職場に連れてくる。これからももちろん父と同じように「継いでほしい」とは言わない。ただ、「自分から継ぎたいと言ってきたとき」かつ「会社がしんどい状況にあるなら継がせてもいい」と考えている。

代表取締役社長 鈴木 史郎氏
(取材/山野千枝 文/山口裕史 写真/福永浩二)
★アンケートやってます★ぜひご協力ください★
https://www.sansokan.jp/enquete/?H_ENQ_NO=22863
☆2月号「ベンチャー型事業承継」特集はコチラから☆
https://bplatz.sansokan.jp/archives/category/201702