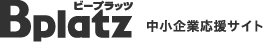【長編】会社を「家族」にするためにどうすればいいか。社長と妻の社内改革奮闘記。
アルミサッシを製造・販売する三島硝子建材は現社長の父・捷義氏が1970年に創業。20代後半に家業に入った三島社長は、2008年に父から会社を継いだ。
いまでこそ社長と社員の関係は良く、ミーティングの状況からも組織のまとまりを感じるが、「私が社長を継いだ当時は違ったんです」と三島社長は振り返る。
同氏が社長になった当時はトップと社員の関係は希薄で、社内の風通しも悪かった。社員同士でさえ仕事の意見や考えを言い合える場も雰囲気もなく、お互いどこか他人行儀な関係だったという。
「私自身、親から会社を継ぎ、敷かれたレールにただ乗っかってるだけの社長でした。経営者として努力が足りなかった。ほんま当時の自分は未熟でした。今もですが(笑)」。

そう打ち明ける三島社長が変わるきっかけは、実修生として受け入れていたベトナム人スタッフのひと言だった。
「この会社、ぜったい潰れます。日本人はベトナム人と仲良くしようとしない。仕事で失敗すれば、理由も言わず怒るだけ。もっと社員同士の絆を持ってください」。
あと半年で帰国するベトナム人実修生3名と三島社長、あゆみさんの5人で食事をした際、彼らからそう言われて「人生が変わった」。
儒教国のベトナムは家族を何より大切にする。そんな国の実修生たちだからこそ、血の通っていない組織に違和感を覚えたのだろう。
実修生たちを迎え入れる組織体制にも問題があった。
ベトナム人たちは技術を学びに来日しているが、技術が求められる仕事は日本人スタッフに割り振り、実修生たちには単純な仕事のみ任せていた。というのも実習期間は3年間。仕事を教えても将来的に会社の利益にならない、そう考えていたからだ。
「いま思えば、当時の私は実修生たちを安い労働力としか見ていなかった。反省しています」。

そもそも、実修生たちとの会食を提案したのはあゆみさんだった。
「私が個人的にベトナム語を学びたいなと思って、気楽に誘った食事会だったんです。ところが、彼らは自分たちの思いを片言の日本語で必死に伝えてくれたんです」。
ベトナム人たちの訴えを聞いたあゆみさんは涙が止まらなかったという。
「実修生たちは母国に残した家族の期待を一心に背負って、希望と不安をかかえながら来日しているんです。そんな彼らの気持ち、何よりベトナムで待っているご家族の気持ちを思うと切なくて申し訳なくて」。
ベトナム人たちの言葉、そして妻の姿に自身の未熟さを痛感した三島社長。
「ちゃんとせなあかん」。

経営塾や研修に参加し、経営者としての自己研鑽に努めるようになった。さまざまな学びを得るなか、改めて顧客の大切さも実感したという。
「たとえばなぜ道具を大切にするのかといえば、お客様に良い製品をお届けするためです。道具を磨けと指示を出さなくても、お客様のことを考えれば自然と道具を大切にするようになる。仕事って、そうやって人の思いを感じながらやると自ずからやることが分かってくる、今ではそう社員たちに伝えられるようになりました」。
次ページ >>> 社長の見守る姿勢、現場は自分の頭で考えるように