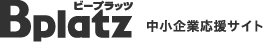≪講演録≫バイオ企業・林原の真実~世界的優良企業「林原」はなぜ銀行に潰されたのか?

≪講演録≫2014年7月24日(木)開催
【社長トークライブ】バイオ企業・林原の真実~世界的優良企業「林原」はなぜ銀行に潰されたのか?
グローバル・リサーチ・アソシエイツ代表 林原 靖 氏
“バイオの雄”として名を轟かせてきた岡山の世界的優良企業「林原」が突然、会社更生法を申請したのは2011年2月のこと。
銀行、弁護士、マスコミの“一方的”な攻撃にさらされた挙句、弁済率93パーセントという不思議な倒産劇があっという間に幕を引いた。
専務取締役として渦中に身を置いた林原氏が「不可解な破綻劇」の真実を語った。
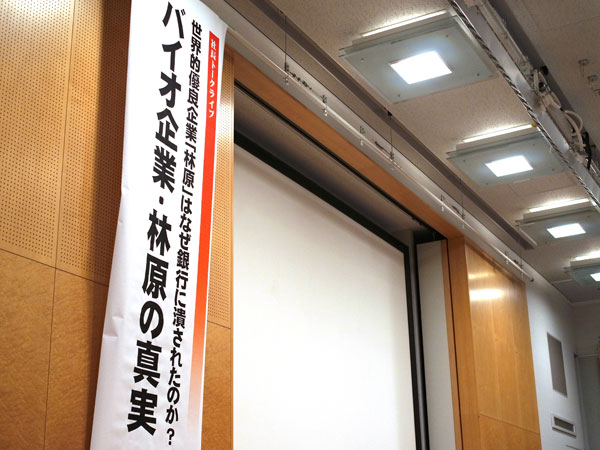
林原は20年~30年ほど前に粉飾決算があった。その点については大変申し訳なく思っており、心からお詫びを申しあげます。ただ、直近のここ10年ほどの事業成績は快進撃を続けていたところでした。つまり20~30年前はそこに至るまでの先行投資の仕込みの苦しい時代で、10年ほど前からようやく回収期に入っていたというのが実態でした。
経営の要諦はスルー・プロスペリティ。儲けながら新しいことをやる、ということです。毎日の儲けの中から投資していくことが繁栄につながる。ただ、林原の研究開発はその範囲を超えたレベルでやらないといけないので、スルー・プロスペリティにならなかった。そこは大きな反省点です。
そして林原は3年前に突然破綻してしまった。破綻の責任は経営者にあるのですが、その破綻劇にかかわった弁護士、会計士、銀行、行政の動きを見ていると不可解なことがたくさんある。私たちが悪いところは悪いと認めたうえで、そこで起きたミスを知っていただき、その上で2度とこのようなことが起こらないようにするための教訓になればいいと考えています。
まるで生体解剖されたような気分
今回の会社更生法の弁済率の数字にまず注目してほしい。93%です。仕入れは全額払っているし従業員の給与も払っています。破綻時に一人も従業員を解雇していません。破綻の時点での債務は銀行、すなわち都市銀行と地方銀行の分しかなく、その額は1300億円。財産などを売り払った結果、銀行にしてみればそのうちの93%を回収できたわけです。
この数字については、私は200%くらい返せていたと考えています。なぜなら資産を極端に安売りしているからです。土地もごく短期間で入札も一切せずに叩き売っている。中国銀行の株式は13%分と大量に持っていましたが、TOBで市場の価格よりも1割強安い価格で売らされました。これだけまとまった株を持っていれば通常プレミアムがつくのですが、ここでも叩き売りをさせられました。子会社の事業価値もしっかり評価されることなく言い値で売られました。
会社更生法の弁済率は通常4割程度なので、93%というのは異常なほど高い数字です。しかも2011年2月に破綻して、最初は事業再生ADRという仕組みに載せようとして失敗した後、会社更生法に切り替えられて破綻からわずか10カ月後の12月には更正手続きが完了しました。管財人は、弁済率の高さと、短期間で手続きが済んだことについて胸を張っていますが、健全会社だったからこそそのようなことができたのです。
直近の10年間で借入金を350億円返していました。資産を売却して換金して捻出したのではなく、通常の商売で得た利益から返していました。この10年間で商売から得られるキャッシュフローは1000億円ありました。つまり毎年100億円のキャッシュを稼いでいたということです。その内3分の1は金利の支払いに充てました。次の3分の1は研究開発費に投資し、残りの3分の1を返済に回していました。そして3億円、5億円といった最終利益を出していました。そのまま順調に事業を進めていけばそのキャッシュは10年で1200億、1500億円になるところだったのです。社員もアクティブな気持ちで世界中に製品を展開していました。
つまり、財産を売ったり、事業をサポートしていただく姿勢があれば破綻は起こらなかった。なぜ、あわてて林原をつぶそうとしたのか。まるで生体解剖されたような気分です。

林原は1886年の創業。破綻した際に社長を務めていた林原健は直系の長男で、4代目の社長でした。私は弟で専務ですが、代表権を持っていたのは健ただ一人。
食品、医薬品の分野で世界初の成果を継続して出していました。病院で点滴を受けるときのブドウ糖は林原が世界で初めてデンプンから高純度のブドウ糖を造る技術を開発し、昭和35年に発売しました。特許が切れてからは過当競争になって林原では製造しなくなりましたが、現在世界中の病院で使われています。
デンプンからつくった高純度マルトースも病院で使われています。デンプンは粒が連なってできているのですが、それを酵素で切って一つ一つばらばらになったものがブドウ糖で、二つずつ切るとマルトースになる。糖尿病患者にはブドウ糖は使えない代わりに、マルトースを使います。
他にも低カロリーの甘味料のマルチトールは、キャンデーやガムの甘味料として世界中で使われています。プルランはデンプンからつくられる多糖類のプラスチックで主として医薬品カプセルの材料として使われています。糖転移ビタミンは、ビタミンCに糖をくっつけることで安定性を増したもので、医薬品や化粧品に使われています。このほかウイルス抑制因子のインターフェロンや新しい甘味料トレハロースも開発しています。小さな規模の会社だが、ブレークスルーを連続し世界に台頭していました。
世間は「林原は研究開発力の強さで儲けている」と言うがそれは間違いです。研究開発力と商売とは関係ない。会社全体の認識から言えば見事なマーケティングをしていたということです。日本、そして世界に広げていく見事なマーケティングのノウハウがあった。それは広報や販売の方法などいろいろあります。

けんかする相手は兄ではなく他にある
私事ですが、本を出しました。一方的なニュースしか出なかったのでつらい思いをしました。悪者にされるのは覚悟の上で甘んじましたが、まったく報道されていないことがあったり、無視されたり、伏せられたこともありました。中小企業を代弁する報道機関がなく、ほとんどのマスコミは中央、大企業、金融機関寄りの姿勢で記事を書いているのは残念です。
たとえば、管財人は第三者委員会をつくるのですが、マスコミはその発表をほぼ鵜呑みにして載せる。だが委員のメンバーを見ると、管財人が所属する巨大な弁護士事務所の弁護士が10人くらい入っています。第三者委員会は弁護士事務所から独立していなければならないはずです。そういうことも調べずに報道をしているのです。
いろいろな事実をまとめて本として出させていただいたので判断はお任せしたい。銀行や管財人にしてみればとんでもない本を出しやがったということになるのでしょうが、趣旨はそういうことです。たくさんの感想をいただきました。自業自得だとか、粉飾をしたのだから何を言ってもだめよといった意見もありましたが、弁護士と銀行が組めば何でもできるんだねとか、破綻にかかわった人たちがその瞬間によかれと思ってやったことが全体として変なことになるおそろしさもあるよねといった意見もいただきました。
最近、兄の林原健が「林原家」という本を出して兄弟のことや同族経営のことを書いています。私は兄とはとても仲良くしていたが、破綻の後疎遠になってしまいました。私の本は小さな出版社から出したのですが、兄は日経BPから出しています。弟が馬鹿な本を出したので、東京の中央としては反論したいという思いがあって、兄の名前で逆の立場の本を出したのかなと思っています。真実は一つなので、両方読み比べていただいて評価を待ちたいと思っています。
ただ一つ辛いのは、あんなに仲のよかった兄と行き来がなくなったことです。これは破綻時の最後の段階で経営陣4人に損害賠償を請求するということになり、そのときに管財人から、「今までは4人1組でやってきたが、損害賠償になると4人の中で利害相反が出る。どうしてもお互いけんかになる話が出てくるので弁護士を分けなさい」と言われました。それを真に受けて一人ひとり弁護士をつけました。それで直接話をしたらいけないということになって弁護士を通してしかコミュニケーションが取れなくなってしまったのです。
兄の本の中で事実と異なる部分があるので、それは私のブログで公開しています。だが、私がけんかする相手は兄ではない。けんかする相手は他にいるのです。

不信感抱いた銀行のビヘイビア(振る舞い)
今回、一番不信感を抱いたのが銀行のふるまいです。自己査定もそのひとつ。林原の資産の評価は非常に低く見積もられました。上場株式もそうだったし、非上場株式に至っては市場で流通できないという理由でゼロとみなされました。お金に換わるものをどうしてきちんと評価してくれないのか。現に新しいスポンサーは700億円で買収に名乗りを上げたわけだから、それだけの価値があったということです。日本は国際的な知的財産評価のルールをまだ取りいれることができていない。林原の場合、おおよそ500億~700億円の特許権、知的財産、ノウハウを評価できたはずですが、日本の銀行はゼロでした。
会計学の後進性も感じます。社員の給料を下げる会社はブラックといわれますが、会計学上、人件費は経費だからできるだけカットしなければいけないと銀行から怒られる。だが働いてくれる社員は大事です。オンリーワンの企業だからがんばってほしい、と思うのなら人材は資産的な価値とみなさなければならない。バランスシートには資産的な要素も加味して表現できるとよい。研究開発費についても同じことが言えると思います。バランスシートにいい人件費と悪い人件費を分けてわかりやすく色づけすればいいと思います。
銀行は信用創造によって無限のお金が生み出されるようにできています。それは私から言わせれば神様から許された神聖な力だと思っているのですが、そう考えたときに銀行のビヘイビアはどうだろう。自分たちの運用の失敗を公的資金で穴埋めしようとするのはいかがなものかと思う。銀行だけが厚く公的資金で助けられて、銀行以外の人はみな泣いているのが日本の現状なのです。
金融の後進性が阻む経営者の再起
アメリカでは、失業して収入がなくなった場合、家を売って立ち退いたら住宅ローンの残債は払わなくてもいいノンリコースローンという金融商品があります。このノンリコースローンを企業の融資にも活用してはどうだろう。となると、銀行には企業を評価する審査の目が求められるのですが、残念ながら日本の銀行にはその目がありません。明らかな怠慢です。日本が再チャレンジできる社会になるにはこれをやらないといけない。損が出た場合はそれぞれが応分に負担すべきです。
生命保険にも問題があると思っています。生命保険の給付金は残された子供の教育費、治療費など最低限の生活費用を確保し、そこから余ったときに回収するようにしなければなりません。そういう引き当てを法律的にすべきです。個人保証も先進国に例のない野蛮な制度です。経営者についてとるのは仕方ありませんが、家族、親戚、知人にはなるべくとるなという指導を金融庁も始めています。私は、経営者からもとらないというのが持論です。破綻のコスト負担は経営者や家族に集中させるのではなく、社会全体で広く薄く負担をさせるようにしないと再登板できない。一回失敗すると立ち直れない。日本で企業の新陳代謝が進まない理由です。
林原の株主は私と兄の2人でした。一般の株式公開会社とは違うわけで、おのずと義務も責任も異なります。とくに中小企業の場合、税務と会計は違うことを弁護士もマスコミもわかっていません。会社法と金融商品取引法がごちゃまぜになって中小企業が守られていないのです。

この破綻でいったい誰が儲けたのか
ほとんどの人が破綻で迷惑をこうむっています。結局誰が一番得をしたのか検証すると、メインバンクである中国銀行と法律事務所です。これは偏見ではなく事実としてです。法律事務所は1300億円ほどの債務額の一定の手数料分を稼いでいるでしょう。取り巻く会計事務所もフィナンシャルアドバイザーも相当巨額な報奨金を得ているはずです。債権ビジネスにかかわるコングロマリットがしっかり儲けているということなのです。
中国銀行にしてみれば債務は全額戻ってきました。林原の持っていた株が全株TOBで自分のものにできたわけで、大株主、目の上のたんこぶがいなくなった。その株を自己消却したので株価が5、6割急騰した。林原が所有していた駅前の一等地再開発については地域商店街を守るために商業施設は入れない計画でした。ところが、破綻後イオンに売られてしまった。中四国最大の商業施設ができる計画です。その結果どうなるか、地元は戦々恐々としています。
現在、中国銀行に対して損害賠償を請求する裁判を起こしました。恨みつらみがあるわけではなく、違法行為があったのでこれについては問う。
ギリシア神話のアイロニーに英雄の悲劇があります。辛い目に遭って命絶たれたり没落したりする英雄の原因を見ると美徳に行き着く。誠実であったり、家族を守るための責任を果たすとか、弱きを助けるという美徳がもとになって悲劇は生まれる。ただその場合、後世になって大切な価値は必ず伝わります。
私は正直すぎると言われます。人のせいにしたり、隠したり、逃げたり、嘘をつけば一時的にはよかったかもしれませんが、その後ろめたさがあれば、こうして今皆様の前で話せるようになることもなかったと思います。事業だから失敗、成功はあります。大事なのはその間をどう過ごしたかなのです。いいときにおごってはだめですが、悪いときにも絶望するなと言いたい。誠実に真面目に一生懸命やっておけば後は何が変わるかわからないのです。
私に起こったことは他人事ではありません。自分がしまったと気づいたときにはもう手遅れです。傍観者ではいけません。よりよい社会にするためにぜひ声を上げてほしいです。