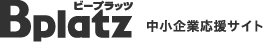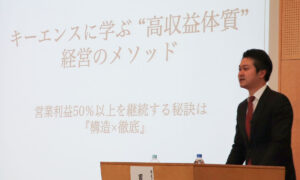《講演録》地酒「獺祭」に学ぶ <伝統の改善>~製造業で実践するには~

《講演録》2021年11月9日(火)
【事業推進セミナー】
地酒「獺祭」に学ぶ <伝統の改善>~製造業で実践するには~
桜井 一宏氏(旭酒造株式会社 代表取締役社長)
人気の日本酒ブランド「獺祭」を製造している旭酒造には、杜氏がいない。徹底したデータ化とアナログな人の力の掛け合わせによって、日本はもちろん世界からも認められる高品質な酒造りを実践しているのだ。今回は、そんな常識破りのモノづくりを先導する旭酒造の代表取締役社長の桜井一宏氏にその方法、哲学、さらにはコロナ禍における取り組みや新たな挑戦について語っていただいた。
◆「獺祭」と他の日本酒の違い
山口県岩国市にある小さな村に私たち旭酒造の酒蔵があります。
旭酒造や地酒「獺祭」については
・高級酒メインの酒造
・純米大吟醸のみをつくっている
・原料となる米は山田錦しか使っていない
・杜氏がいない酒蔵
・海外でも人気で輸出に強い
といったポジティブなイメージを語っていただくことが多くあります。新潟大学日本酒学センターの岸保行教授からは「優秀なビジネスモデル」と評していただいたこともあります。
一方で
・オートメーションで大量生産している“らしい”
・工業的に大量生産している“らしい”
そして
・大量に造りはじめて味がおちた“らしい”
といった少し実態とはズレた誤解をされているという声も耳にします。
では実際、どのような酒をどのように造っているのか。ご説明していきたいと思います。
私たちが造る酒に使用している米は「山田錦」です。山田錦は、粒が大きく磨きやすいために“米を磨く”純米大吟醸に適しています。この山田錦のみ使う、さらにその米を50%まで磨き、醸造用アルコールを添加しない「純米大吟醸」しかつくっていない、というのが私たちの酒蔵の大きな特徴です。醸造用アルコールを添加した精米歩合の指定がない「普通酒」をメインで製造し、それ以外の特別な酒は少し製造する、という酒造さんが多い中で、我々は珍しい形態です。
※酒税法上「純米大吟醸」に分類されない商品も一部あり

その他、他の酒造さんとの違いについてご説明します。
まず、製造方法について違いがあります。他酒造さんは普通酒では機械も使用し効率的に製造し、良いお酒は伝統的な手造りを採用しているところが多いですが獺祭は“伝統も機械もデータもなんでもあり”で製造しています。また、獺祭は一年中製造しています。この点は、大手酒造さんも同じですが中小酒造さんは冬季がメインのところが多いです。そして、大きく違うのが製造サイクルです。規模によりタンクサイズの大小はありますが他酒造さんの製造サイクルは、年に数回から多くて数百回です。一方、獺祭は比較的小規模なタンクにて年3000回のサイクルで製造しています。年間3000回……、それは一般的な酒蔵の100年分以上に相当する異常な回数です。
もともとは私たちもひと冬に17~18回ほど普通酒を、一度ほど本醸造を仕込むという酒造でしたが、右肩下がりの日本酒業界とともに……というよりも、さらに早いスピードでどんどん売上げが下がっていました。そんな中、営業努力が必要だということで私の父がさまざまな場所に営業に赴いていましたが、ほとんどの地域で響きませんでした。しかし、東京市場だけは違いました。山口県出身の大将が営む飲食店や酒屋などをきっかけに徐々に品質に対する評価をいただけるようになり、受け入れられていったのです。バブル期のはじまりで「高くてもいいから良いお酒を」というお客様がちょうど増えてきた時期でした。品質勝負で市場を切り取るという成功体験を得たこともあり「獺祭」が平成2年に誕生しました。その後も品質にこだわった酒を増やしていき、なおかつ製造本数も増やしていこうとした結果、年間3000回製造する現在のようなスタイルに近づいていきました。

◆杜氏がいないから“伝統も機械もデータもなんでもあり”
先ほど獺祭は“伝統も機械もデータもなんでもあり”で製造しているとお伝えしましたが、どういうことかをご説明します。まず、麹造りです。これはまさに人海戦術です。麹造り用の機械も販売はされているのですが、使用していません。米をほぐして一粒一粒麹菌を米に植え付けていくには、色んな環境に順応しやすい人の手が一番麹造りに適した“機械”だと考えているからです。湿度が高い部屋で大変な作業ですが、すべて社員が行っています。次に、タンクで酒を造る工程。これは、機械化とアナログのハイブリッドです。部屋の温度を年間通して6度に設定して、その中で社員がアナログに酵母の様子を見ながら発酵のコントロールをしています。一部屋にタンク100個、それが3部屋、計300個のタンクを順繰りに使っていって、年間3000回の仕込みを可能にしています。これだけの数があるから人数も必要です。そのため、弊社の社員数は230名中、製造メンバーは約130名にものぼります。このタンクひとつひとつは毎日、成分分析をしてデータをとっています。そして、人間が味見をします。先代、私、製造部長、工場長、副工場長で毎日味を見ています。「今日の味はなぜこうなのか」という答合わせはデータでできます。人の味見、データそれらを掛け合わせて明日の酒造りをどうしようかということを決めていっているのです。つまり、フルオートメーションでもなければ、すべてアナログでもない。人の力、機械やデータの力、どちらも良い酒造りのための手段です。

◆ブラックボックス化していた伝統の技を「見える化」
かつて、酒の味というのは杜氏が握っていました。もともとは季節雇用の杜氏さんを雇って冬だけに酒造りをしていたのですが、弊社の地ビール事業の失敗をきっかけに杜氏が辞めていき、当時の社長である私の父が杜氏の役をやらざるを得なくなりました。そんな中で、仕込みの内容、酒造りでやっていったことを見える化し、酒の味という結果をもとに検証していった。これが結果的に現状のスタイルにつながりました。
本来、杜氏は季節雇用の個人業が多いので自分の酒造りのノウハウは外に出しません。そして、ある年の酒の出来が良くなかったとしても、米のせい、精米のせい、麹のせい、はたまた“酒造りの神様が今年は機嫌が悪かった”などといくらでも言い訳ができてしまう。そんなブラックボックス化されていた杜氏の技、経験と勘をできるだけ言語化、見える化したのがデータです。データと実際の味を年3000回という数だけPDCAを回す。ABテストや実験をする。いわば、この回数分だけアジャイル手法(さまざまな状況変化に対応しながら開発を進めていく手法)で改善していくことができたのです。その結果、いいも悪いも経験が蓄積し、ノウハウを得ていくことができました。一方、同じ地域、同じ年度の米、同じ発酵経過で同じようなデータなのに味が違うといったことが起こることもわかりました。“見える化”したからこそ、現時点で“できないこと”がわかったのです。でもそれも、データを丹念にとり、試行錯誤していくことによってその先へいくことができるのではないかと考えています。ありがたいことに、このようなモノづくりのスタイルが受け入れられて、日本酒全体の右肩下がりの状況とは反比例して獺祭の売上げは伸びています。海外市場でも受け入れられており、前年度の日本酒総輸出額241億円中、弊社は35億円を占めました。今年度はさらに伸長し、69億円を記録しています。

2022年、ニューヨークで醸造を開始する予定です。現地で育てられた山田錦、現地の水、そして日本からも社員が行きますが、現地の人も雇用して現地でつくるミックススタイルを想定しています。日本とはさまざまなことが違うので、また試行錯誤になるということから、我々の酒造りにとっては価値のある場所になることを確信しています。だからこそ、ブランド名を「獺祭Blue」と名付けています。「青は藍より出でて藍より青し」との言葉の通り、日本の獺祭を超えたものをつくってやるぞ、という気持ちを込めています。
◆新型コロナウイルスの打撃と在庫
新型コロナウイルスの感染拡大に関しては、最初は対岸の火事で、中国市場の輸出が落ち込む程度でした。しかし、やがて中国からヨーロッパへの感染拡大がはじまると一気に影響が出てきました。売上げは前年比40%を切り、免税店の売上げは99%ものマイナス。そこで、製造に一気にブレーキをかけました。社員の多くを休ませる、先ほど言及しましたニューヨークの醸造所の工事も一年凍結。でも、そうこうしているうちに先に感染状況が改善したアジアをはじめとした海外市場の需要が一気に戻ってきました。ところが、製造にブレーキをかけていたから供給できない。製造後2~3ヶ月で出荷できるため即座には対応できない状況があり「なんで商品を提供しないんだ」というお叱りも受けました。そのように海外の動向によりコロナの影響がどのように日本にも波及してくるかが予想できたため、早めに有利な条件で借り入れを受けることができたのは不幸中の幸いでした。
◆生産者も飲食店もなくてはならない存在だから
製造にブレーキをかけたので、原料である山田錦の在庫をたくさん抱えていました。そのため、社内でも今後の入荷量を抑えるべきだという声も出ていたのですが、山田錦の生産者さん達は私たちにとって大切な存在。サプライヤーさんが健全な状態でないと、私たちも今後モノづくりができません。そこで、生産者さんに対しては向こう3年間今までと同じ量を入荷し続けますよ、とお伝えしました。当然、余った山田錦をどうするんだ、ということになります。色々思案した結果、山田錦を使用したアルコール消毒「獺祭タノール」を生産したり、「獺祭の酒米」という食用米にして販売したりすることにしました。正直、儲けが出ない商品ではありましたが、お米は使えるし、社員も家で休ませておくよりもいいだろうと。また、私たちにとってサプライヤーさん同様、大切な存在が飲食店さんです。飲食店さんを支援したいという思いから2021年5月24日に日経新聞に意見広告を出しました。飲食店にはとりわけ厳しい制限策が強いられていた中、【このままでは、飲食店がコロナ禍の最大の犠牲者に】、【感染も倒産も抑えるために、意味のある制限策に見直して欲しい】、【地域経済の復活なしに日本再生はあり得ない】といった章を立てて、“飲食店を守ることも「いのち」を守ること。私たちは、日本の飲食店の「いのち」と共にあります。”と意見表明しました。ありがたいことに、多くの共感をいただきました。

◆コロナ禍で気づいたこと、これからの酒造り、人づくり
このコロナ禍で私たちは、自分たちのいくべき方向を考え直す機会を得たと思っています。コロナ前まではマス寄りの商品を生産していく方向に感覚的に引っ張られている部分もありましたが、世界的に飲食のシーンは飲む回数は減り外食は「ハレの日」に、という傾向になったと考えています。そんなときに、やっぱりいい酒を飲みたい。そういう需要に応えるためにも、やはり高付加価値方向の市場で攻めていくのが我々の本分だと考え直しました。2020年10月には香港のオークション「サザビーズ香港」に、私たちがコンテストで選んだ最高の山田錦から造った高品質な「獺祭」を出品し、最高6万2500香港ドル(約84万)で落札されました。残りの数十本も、日本国内でも売り切れました。驚きの結果でしたが、やはり高付加価値の商品は求められているのだと実感しています。
いい商品をつくるには、製造の根幹を強化する必要があります。そこで、何よりもまず最高のモノづくりをするプロの職人に報いることが必要だと考えました。仕事に求めることは、やりがい、誇り、いろいろありますが、まず目に見えるところからということで社員の所得を5年で倍にすることに決めました。今、段階的に給与を上げていっているところです。既存の社員だけでなく新入社員の初任給も同じです。いい人材を確保することで社内に刺激を与え、さらによいモノづくりに挑戦していきたいと考えています。
(文/今中有紀)
 桜井 一宏氏(旭酒造株式会社 代表取締役社長)
桜井 一宏氏(旭酒造株式会社 代表取締役社長)
1976年、山口県生まれ。2003年に早稲田大学社会科学部を卒業し、他社を経て2006年に旭酒造へ入社。製造部門での修業を経て、2016年に代表取締役社長に就任、以来現職。