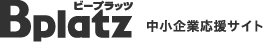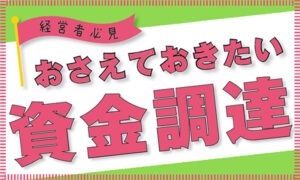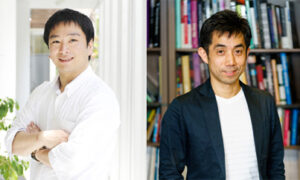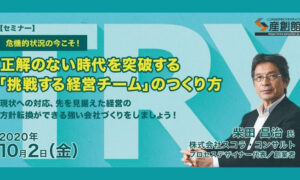《講演録》3人のプロに学ぶ!データから「価値」を見出すセンスの磨き方

2022年7月15日(金)開催
【デジタル推進セミナー】
3人のプロに学ぶ!データから「価値」を見出す センスの磨き方
■講師
伊藤 將弘氏(立命館大学生命科学部生命情報学科教授)
殿村 裕一氏(ダイハツ工業株式会社営業CS本部国内商品企画部主査)
深井 翔氏(CCCマーケティング株式会社CCCマーケティング総合研究所ユニットリーダー)
IT化の進展で、企業には売上数字や顧客情報といった多種多様なデータが日々生み出されている。数値に過ぎないデータをどのように読み解き、企業経営に生かせばよいのだろうか。「データサイエンス」「自動車づくりとファン作り」「データの事業活用」の”プロ”である3人に、データの活用方法、そしてデータを「可能性を秘めた宝の地図」とする方法について語ってもらった。
◉生命情報学の観点から見た経営(伊藤 將弘氏)
私はバイオインフォマティクスを専門としています。今日は「データは宝箱だ」という話をしたいと思います。「最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは変化できるものである」いう話もありますが、現代においてデータはこの「変化」に直結するものだと思います。
遺伝学の父であるメンデルは、えんどう豆を使った実験から遺伝の法則を見出しています。高校で詳しく学びますが、えんどう豆は種子が丸いものと種子にシワがあるものがおおよそ3:1の割合で出現します。種子の色が黄色か緑色かであるかも3:1。そのほかにもさまざまな特徴が3:1の割合になっています。この割合をメンデルはたくさんのえんどう豆を集めてきて1つずつ分類し「見える化」することから始めました。つまり、えんどう豆の特徴を「数値化」したのです。ここから彼は「優性」と「劣性」という考え方を見つけました。
えんどう豆の個体の特徴を「表現型」と呼びますが、この表現型は企業で言えば売上とか、利益とか、目に見えることに置き換えられるでしょう。つまり、企業においても、問題となることをまず数値化する。いくつの事例のうち、いくつ問題が起きたのかを見える化することで、そこから「解析」を行うことができます。
なぜ3:1の割合になるかを、メンデルはえんどう豆の遺伝の法則性で説明しました。法則性が分かれば、次の世代にどういう表現型が生まれてくるかも大方予測することができます。私はこうしたデータサイエンスはマーケティングでも同じだと考えています。二つの事例を比較して、何が違いを生み出しているのかは、二つの事例をAというデータとBというデータにして比較する。ただし、データが教えてくれるのはそこまでです。その違いに意味付けをするのは私たち自身であり、その意味付けから新たな商品企画へとつなげていくのは皆さんだということです。こうしてみたとき、データは宝物がつまった箱のようなものだと言えると思います。
◉「どぶ板調査」で見つけたデータを新商品に(殿村 裕一氏)
ダイハツ工業株式会社でデータを活用した商品企画を行っています。特に商用車とスポーツカーを担当しています。変な組み合わせに思えるかもしれませんが、この二つに共通していることは、「使われ方が明確」だということです。
データ収集については、私たちはよく地道にコツコツと行う調査、いわば「どぶ板調査」を行っています。月に1万台以上売れている車であれば定量調査でも大量のデータが集まりますが、月500台ほどでは、使われ方が1台1台異なります。だから聞きに行くしかない。定量調査では聞けない、顧客の生の声を聞くためにこういった調査を続けています。
昨年12月にリニューアルして発売した商用車では、社員3人で大企業から農家の方まで30社125名の方に直接お話を伺い、商品企画を立てました。その中でわかったことは、運輸業ではコロナ禍以降、ネット販売の増加にともなって荷物の量が激増しているということです。でも、運んでいるものを見ると、段ボール箱の大きさは大体4種類。それをドライバーさんたちは1日8時間で150個運ぶことが1つの指標になっています。
一方、小売業も運輸業化しつつあります。コンビニが自宅まで商品を届けてくれる。これはつまり、プロのドライバーではない人、パートやアルバイトの人も運転するということで、ドライバーの多様化が進んでいます。この現象は、法人化された大規模農地にも見られました。したがって、これまでより運転のしやすさが求められていたのです。商用車のリニューアルを検討する際には、調査で得たこうしたデータを元に商品企画を立て、開発担当者とも検討を重ねました。
このように顧客の要望を愚直に商品に反映させた結果、アトレーという乗用タイプのワンボックスは売上が10倍に伸びました。この車種は90年代以降新たに開発されることもなく、社内でも「いらないのでは」という話すら出ていたのですが、先程のニーズに加えて、釣りやキャンプといったアウトドア市場の伸びも調査からは見え、顧客ニーズの変化をデータで示した結果、ニッチな市場に割り切り、目的をはっきりさせるという最適化で売上を伸ばすことができました。オンラインの定量調査でデータを集めることもできますが、まずは自分が聞きに行くということも非常に大切ではないかと感じます。
◉定性データ×思考力=自社の企画力(深井 翔氏)
CCCマーケティング株式会社で、約7,000万人のT会員のデータを扱っています。多くの経営者がデータを有効活用したいとか、データで事業を安定させたいとか、変化する消費者ニーズに合った商品開発をしたいという思いを持たれています。一方、私どもは年間50億件の購買履歴というビッグデータを持っています。ここから消費者のニーズに合致した企画やサービス、PRが簡単に実現できると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、データの種類や特性をよく理解しないと、こうした発想は大きな落とし穴にはまってしまうという危険性もはらんでいます。実際に私自身も商品開発に失敗した経験があります。
「定量データ」とは、商品の市場占有率や売上高などに基づいて消費者行動の広さを把握するものです。一方「購入した商品の何が気に入ったか」「なぜこのお店で買ったのか」「パッケージデザインは使いやすいか」といった数値に表せない質的な情報は「定性データ」といい、消費者行動の深さを見ることができます。
定量データは、人々が行動した後の履歴を集めたようなもので、今現在「見えている」データだといえます。私はこの「今の時点でわかっていること」を「将来必要とされるだろうもの」に結びつける力が大切だと思います。たとえば温水洗浄便座は顧客が「欲しい」と言ったわけではなくて「こういうものがあったらいいよね」という想像から作られています。データから潜在的なニーズにつながる道筋を探すことが重要なのです。
私の失敗の事例を紹介すると、非常に売れている商品に負けないダウンジャケットを開発しようとした量販店PB開発チームで、定量データ分析と定量調査を徹底的に行なった結果、あることがわかりました。それは「薄くて軽くて温かいダウンジャケットが求められている」ということ。つまり、ライバル品と同じだったのです。現状のニーズを知りつつ、自社の強みや、今後発展しそうな潜在ニーズを検討せず、データだけに答えを求めようとすると、結局はこのように差別化ではなく同質化してしまうという失敗は、データ活用の悪例でもあります。
企画の質は「定性データ」と「思考力」の組み合わせが肝だということです。お惣菜の唐揚げを開発した際、定量データからは女性は「サクッとじゅわっと」「できたて」といったことを支持するとわかりましたが、これでは他社との差別化にはつながりません。一方、生活者へのリアルなインタビューでは「スーパーの惣菜は家族向けに」購入している女性が多くいることが分かりました。その結果、スーパーの惣菜唐揚げのニーズたる家族みんなで食べやすい「薄衣」「やさしいがしっかりした味付け」を追求したところ、売上が200%増加しました。
定性調査は、どのような企業でも行うことができますのでぜひ行うことをおすすめします。そこから得られた定性データを活用する思考力は、自社の企画力に直結します。加えて、世代を超えて企業が進化するためには、デジタルによる見える化も非常に重要なポイントだと考えます。
◉トークセッションから
深井:ダイハツの調査の考え方について、もう少し詳しく教えて下さい。
殿村:よく言われることに、マーケティングの3Cと呼ばれる「カンパニー」「カスタマー」「コンペティター(競合)」があります。この競合他社は異業種であることもよくあって、たとえば、200万円の現金があれば車より腕時計を買ったほうが価値が落ちないと考える人もいます。そういう意味で、自動車の競合は腕時計だともいえるかもしれません。データを前に頭が混乱したときには、この3Cに戻るようにしています。
深井:調査でも3Cを意識したフレームを使われているのですね。
殿村:はい、でも市場環境がどんどん変わっていくのでそれにあわせてフレームの中身は変えていくようにしています。
深井:個人的に気になっているのですが、野球などのスポーツもデータで語れると言われます。マーケティングだけではなく、今後さまざまな分野でデータ活用が進むと思うのですが、伊藤先生は学生などと話す中で、どのように感じますか。
伊藤:野村克也監督がID野球ということを言われていましたが、たとえばあるバッターが特定のカウントで特定のコースをスイングする確率は○%、というようにかなりの部分で法則性を見つけることができると思います。将棋の世界でもAIが進化していますよね。でも、AIと対戦したある棋士が誰もが成る「と金」にならなかったとき、そうした不規則なデータに対応できなかったAIが投了したということがあったそうです。AIは過去のデータから未来を予測しているわけですが、過去にはなかった新しいファクターを加えることによって、また変わった展開ができるということもデータサイエンスの面白さかなとも感じます。
深井:企業で言えば、値付けにもデータが活用できますよね。ただ、これも私の失敗談なのですが、以前ウェブアンケートである量販店の商品を「いくらなら買いますか?」と尋ねたことがあります。結果、当然ながら安いところにウェイトが立っただけで、価格そのものをデータで決めることは難しいのだなと感じました。
殿村:そうですね、そういう尋ね方だとうまくいかないかもしれませんね。でも、たとえば傘だと、60センチ、70センチ、80センチの傘、10センチずつの違いで、それぞれお客さんはいくら払うのかをデータ化するといったことならできるかもしれませんよね。
会場からの質問:水運観光事業をやっているのですが、たとえば沈む夕日を顧客に見せて「これが最も美しいと感じさせられる夕日だ」ということをデータ化して、そこからサービスを商品化することは可能だと思われますか?
深井:非常に面白いアイデアです。例えば1つのモノを買うとき、それをめちゃくちゃ愛している人と、ただなんとなく購入した人の間に、どのような差があるのかを数値化する取り組みをまさに最近行っています。私どものTSUTAYAは、書籍などのモノではなく「場所」を愛してもらうということを事業の根本に据えています。ですので、インタビュー調査などを通して、商品や場所に対するその人のパッションのようなものをランク付けというか見える化することで、より愛してくださっているお客様にさらに詳しく情報をお聞きしたり、アドバイスをいただいたり、逆に我々が何かを返していくようなことができていくのではないかと考えています。まだ、「そういうことができたらいいな」という段階ではあるのですが。
殿村:結局、データは過去にどれくらいの購買があったのかといったものを集めたものなわけですが、これからどういうモノやサービスをつくっていくかを考えるときには、数値だけではなくやはり情熱とか愛情というものも必要だと思うんです。そういう熱量で生み出したプロダクトやサービスというのは必ずお客様にも伝わると感じます。特に観光のような部分に関しては、モノよりも体験にお金を払う時代になっていると思うので、結局のところそうした熱量が重要になるだろうという気がします。
(文/安藤智郎)
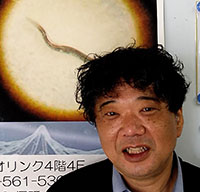 伊藤 將弘氏(立命館大学 生命科学部 生命情報学科 教授)
伊藤 將弘氏(立命館大学 生命科学部 生命情報学科 教授)
博士(情報科学)。国立遺伝学研究所から2004年立命館大学に赴任。2012月4月より現職。専門は生命科学と情報科学を融合した生命情報学(バイオインフォマティクス)、ゲノム科学、データサイエンス。新型コロナウイルスに関して2020年3月に研究結果を日本でいち早く世界に発信した。
 殿村 裕一氏(ダイハツ工業株式会社 営業CS本部 国内商品企画部 主査)
殿村 裕一氏(ダイハツ工業株式会社 営業CS本部 国内商品企画部 主査)
三菱自動車から2007年転職し、中途採用にてダイハツ工業に入社。パリ・ダカールラリーや世界ラリー選手権のエンジニア経験もある自動車業界でも珍しいマーケッター。自らが開発に携わった「コペン」で2021年JAF全日本ジムカーナ選手権JG10クラス年間ランキング3位獲得するなど、開発・マーケティング・エンジニアリングとマルチに手掛けるほか、商用車の商品企画も手掛ける。
 深井 翔氏(CCCマーケティング株式会社 CCCマーケティング総合研究所 ユニットリーダー)
深井 翔氏(CCCマーケティング株式会社 CCCマーケティング総合研究所 ユニットリーダー)
2006年ハイファッションブランドの専門商社へ入社後、ブランドのマーチャンダイジング、バイイングを担当。2014年より、日本大手流通企業のPB開発・MD領域のコンサルティングに従事、服飾雑貨を中心に年間100案件を超えるPB開発を行う。2019年よりCCCマーケティング株式会社に入社。生活者のデータを軸として活用した、大手流通小売企業の商品企画を担う。