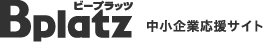研究機関の独自技術でイチジクの保存力アップ

果肉が軟らかく保存がきかないイチジクは消費地に近い都市部の近郊で栽培されることが多く、中でも南河内エリアにおける栽培量は今なお関西随一を誇る。傷んだところがすぐに変色し商品価値を失った大量のイチジクが廃棄される運命にあることを知り、なんとか菓子作りに活用できないかと奥田氏は考えた。
だが、生産者泣かせのイチジクは菓子職人をも困らせた。炊いても、炊いても水分があふれ出てくるのだ。最初にイチジクのパイで商品化を試みたが、パイ生地が湿って商品にならなかった。結局炊いては砂糖を入れ、を4日間繰り返すことでようやく商品として使えるようになったという。その後、イチジクのゼリーやイチジクをあんにして入れた三笠などを商品化。「大阪産(もん)」のブランドを使った菓子は人気商品として定着している。
他にイチジクを使った商品作りができないかと考えていた奥田氏の目に留まったのが、グラッセ。グラッセは、素材の表面につやが出るほどに甘く煮詰めたフランス菓子だ。日本でもイチジクグラッセは少量出回っているが外国産のイチジクが使われていることが多く、これを南河内産イチジクで作れないかと考えた。ここでも苦労したのは「水分量」だ。「水分が残っていると菌が発生しやすく消費期限が短くなってしまう。かといって、水分を飛ばしすぎてしまうと乾いて食感が悪くなってしまう」。
協力を仰いだのが、大阪府立環境農林水産総合研究所。食品の乾燥技術のスペシャリストと2人3脚で、乾燥機の温度設定、乾燥時間を調整しながら「クッキーが含んでいるくらいの」最適な水分量に導く乾燥法を探り当て、賞味期限を約3カ月もたせる製造マニュアルを作成した。今夏に収穫されたイチジクを使って、ラム酒やブランデー、ワインにつけ、ホワイトチョコレートをかけたグラッセの商品化を視野に入れている。
もう一つ、同研究所と連携して進めているのが、日本ではほとんど栽培されていないイスキア・ブラックというイチジクを使った商品の開発だ。生産者にとっては病害に強く、傷みにくく扱いやすい。加工者にとっては小ぶりながら甘味が多く、菓子や料理作りに向いているとされる。イチジク農家が減少傾向にあるが、「うちが菓子に使うことで消費量の多い料理の世界にも広げていければ、おのずと地元の農家で栽培するところも増える。いい循環を回していきたい」。これからも地域の元気につながる商売にこだわり続けていく。

▲研究所と連携して商品開発に取り組む。

▲富田林市の本店。

▲イチジクを約4日間煮詰め、水分を飛ばすことでようやく素材として使えるようになる。

▲はじめてのイチジクを使った商品「いちじくパイ」とイチジクを丸ごと入れたイチジクゼリー。

▲代表取締役 奥田 辰造氏
株式会社かつら屋
代表取締役
奥田 辰造氏
設立/1964年 資本金/1,000万円 従業員数/30名 事業内容/富田林市に本店を置く和菓子店。本店のほか羽曳野市、柏原市に店舗を計4店展開している。定番のまんじゅう、もなかのほか、ぶどう大福や栗パイなど幅広い品揃えで地元の顧客から支持されている。