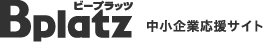今さら聞けない「令和=何年?」問題、和暦と西暦の“変換モヤモヤ”を解決する仕事術
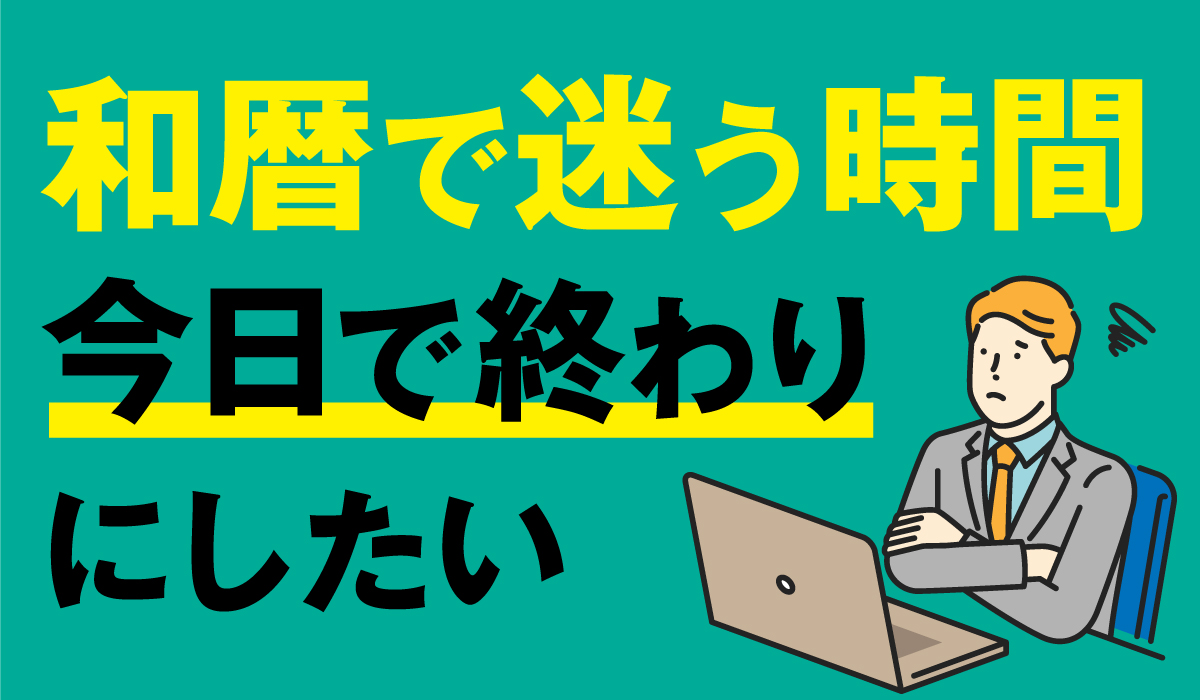
「2025年って令和何年?」
「平成30年って西暦何年だっけ?」
「契約書の日付が“和暦”指定なんだけど、自信ない…」
日々の業務の中で、ふと立ち止まってしまう“和暦と西暦の変換”。
ビジネスの現場では、見積書や契約書、申請書類、さらには履歴書など、思わぬ場面で元号表記が必要になります。にもかかわらず、毎回スマホで「平成 何年 西暦」などと検索している人も多いのではないでしょうか。下記に早見表を記載していますのでご参考ください。
目次
西暦和暦早見表【2025年最新版】
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 昭和元年 | 1926年 |
| 昭和2年 | 1927年 |
| 昭和3年 | 1928年 |
| 昭和4年 | 1929年 |
| 昭和5年 | 1930年 |
| 昭和6年 | 1931年 |
| 昭和7年 | 1932年 |
| 昭和8年 | 1933年 |
| 昭和9年 | 1934年 |
| 昭和10年 | 1935年 |
| 昭和11年 | 1936年 |
| 昭和12年 | 1937年 |
| 昭和13年 | 1938年 |
| 昭和14年 | 1939年 |
| 昭和15年 | 1940年 |
| 昭和16年 | 1941年 |
| 昭和17年 | 1942年 |
| 昭和18年 | 1943年 |
| 昭和19年 | 1944年 |
| 昭和20年 | 1945年 |
| 昭和21年 | 1946年 |
| 昭和22年 | 1947年 |
| 昭和23年 | 1948年 |
| 昭和24年 | 1949年 |
| 昭和25年 | 1950年 |
| 昭和26年 | 1951年 |
| 昭和27年 | 1952年 |
| 昭和28年 | 1953年 |
| 昭和29年 | 1954年 |
| 昭和30年 | 1955年 |
| 昭和31年 | 1956年 |
| 昭和32年 | 1957年 |
| 昭和33年 | 1958年 |
| 昭和34年 | 1959年 |
| 昭和35年 | 1960年 |
| 昭和36年 | 1961年 |
| 昭和37年 | 1962年 |
| 昭和38年 | 1963年 |
| 昭和39年 | 1964年 |
| 昭和40年 | 1965年 |
| 昭和41年 | 1966年 |
| 昭和42年 | 1967年 |
| 昭和43年 | 1968年 |
| 昭和44年 | 1969年 |
| 昭和45年 | 1970年 |
| 昭和46年 | 1971年 |
| 昭和47年 | 1972年 |
| 昭和48年 | 1973年 |
| 昭和49年 | 1974年 |
| 昭和50年 | 1975年 |
| 昭和51年 | 1976年 |
| 昭和52年 | 1977年 |
| 昭和53年 | 1978年 |
| 昭和54年 | 1979年 |
| 昭和55年 | 1980年 |
| 昭和56年 | 1981年 |
| 昭和57年 | 1982年 |
| 昭和58年 | 1983年 |
| 昭和59年 | 1984年 |
| 昭和60年 | 1985年 |
| 昭和61年 | 1986年 |
| 昭和62年 | 1987年 |
| 昭和63年 | 1988年 |
| 昭和64年/平成元年 | 1989年 |
| 平成2年 | 1990年 |
| 平成3年 | 1991年 |
| 平成4年 | 1992年 |
| 平成5年 | 1993年 |
| 平成6年 | 1994年 |
| 平成7年 | 1995年 |
| 平成8年 | 1996年 |
| 平成9年 | 1997年 |
| 平成10年 | 1998年 |
| 平成11年 | 1999年 |
| 平成12年 | 2000年 |
| 平成13年 | 2001年 |
| 平成14年 | 2002年 |
| 平成15年 | 2003年 |
| 平成16年 | 2004年 |
| 平成17年 | 2005年 |
| 平成18年 | 2006年 |
| 平成19年 | 2007年 |
| 平成20年 | 2008年 |
| 平成21年 | 2009年 |
| 平成22年 | 2010年 |
| 平成23年 | 2011年 |
| 平成24年 | 2012年 |
| 平成25年 | 2013年 |
| 平成26年 | 2014年 |
| 平成27年 | 2015年 |
| 平成28年 | 2016年 |
| 平成29年 | 2017年 |
| 平成30年 | 2018年 |
| 平成31年 | 2019年 |
| 令和元年 | 2019年 |
| 令和2年 | 2020年 |
| 令和3年 | 2021年 |
| 令和4年 | 2022年 |
| 令和5年 | 2023年 |
| 令和6年 | 2024年 |
| 令和7年 | 2025年 |
ビジネス現場で起きている「和暦迷子」たち
例えば、2025年は令和7年。一度調べても、しばらくするとまた忘れてしまいます。
ある企業の人事担当者の話では、学生アルバイトが提出する履歴書で、和暦・西暦の混在によって誤記の発生や、行政への申請書で形式不備となるケースもあるようです。これは学生アルバイトに限った話ではなく、日付表記が厳密に求められる契約や行政手続き等でも同様の問題が起きているとのことです。
「昭和→平成→令和」の基礎知識
まず、ざっくりと現代の元号と対応する西暦を整理しておきましょう。
| 元号 | 開始年(西暦) | 終了年(西暦) |
|---|---|---|
| 昭和 | 1926年 | 1989年 |
| 平成 | 1989年 | 2019年 |
| 令和 | 2019年 | 継続中 |
※「平成は何年まで?」という疑問には、平成31年(=2019年4月30日)が答えとなります。
※また令和は2019年5月1日から始まっています。
よくある間違いと「和暦変換」あるある
●あるある①:「R5」「H30」などの略号に混乱
履歴書や社内文書で使われがちな「R=令和」「H=平成」「S=昭和」。
一見便利ですが、外部とのやりとりでは誤解を招く原因にもなります。
●あるある②:年の変わり目での年度ズレ
例えば、令和6年(2024年)でも、3月末までは前年度扱いの場合があります。
「年度」と「年」は一致していないことも多いので注意が必要です。
●あるある③:システムやフォーマットが未対応
Excelや会計ソフトが古いバージョンのまま、和暦表記に対応していないケースもあるのでご注意ください。
いますぐ業務に使える「和暦⇔西暦」変換の2つのコツ
① ざっくり暗記する計算式を使う
平成 → 和暦+1988(例:平成30年+1988=2018年)
令和 → 和暦+2018(例:令和7年+2018=2025年)
②Excel関数を活用する
Excelでは以下のような関数で変換が可能です:
—————————————————
・TEXT関数
=TEXT(A1, “ggge年m月d日”)
→ セルA1の日付を和暦で表示できます。書類や履歴書などで和暦表記が必要なときに便利です。
※データに合わせてA1のセル番号を該当のセルに調整してください。
・TODAY関数(+TEXT関数)
=TEXT(TODAY(), “ggge年m月d日”)
→ 資料などの日付をいれたいセルにこの関数をいれておけば、今日の日付を自動で取得し、和暦で表示します。日付を毎回更新しなくてもいいので便利です。
・DATE関数
=DATE(2025, 5, 1)
→ 「2025/5/1」という日付を作成します。特定の日付を入力したいときに使います。
—————————————————
和暦はいつまで使うのか?デジタル化との共存
「和暦があることで逆にややこしい」という声も聞かれますが、公文書や行政手続きでは依然として和暦表記が主流です。特に年配層や伝統産業、地域行政など、元号を基準に歴史を捉える場面が多く、上手に付き合っていく必要がありそうです。
社内の“元号ルール”、そろそろ見直しどきかもしれません
日々の業務における小さな混乱は、放置すると大きなミスにつながることがあります。
「社内フォーマットは西暦で統一する」「略号(R・H)ではなく正式な元号を使う」「誰でもすぐ確認できる早見表を共有する」——。
どれもささいなことですが、こういった社内ルールの整備こそが、チーム全体の作業効率を高める第一歩となることもあります。これを機に、社内の“元号のマナー”を見直してみてはいかがでしょうか?