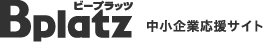【長編】「自転車に乗ってどんな満足感が得られるのか」

成熟市場といわれる自転車市場に、8年前に新規参入したブランド「ドッペルギャンガー」は業界に風穴を開けた。「我々が売っているのは自転車ではなく、コンセプト」とライフスタイルを見据えた商品開発でカテゴリートップの商品を次々に送り出している。「メーカーと消費者の間にあるギャップがまだまだある」と自転車市場における新たなビジネスチャンスに見据える益田氏に自転車づくりに込めた思いを聞いた。
―ドッペルギャンガーが誕生した背景は?
私どもが商品開発にあたっていつも考えていることは、需要と供給、つまり買う側とつくる側のギャップがあるところにチャンスがあるということです。
例えば、当社の商品に「パソコン用のチェア」や「簡易なテント」、「手足がついた身動きのできる寝袋」などがあります。従来のオフィス用のチェアは机に向かって手書きでものを書く姿勢を前提につくられており、パソコンを打つ姿勢に合ったものがありませんでした。また、1人で山に登りマイナス何十度のところで死なないために、寝袋やテントがつくられていたわけですが、今、時代が変わり誰でもキャンプをするようになっています。手軽に河原でキャンプを楽しむ人たちにとって設営に30分もかかるようなテントはオーバースペックです。車中泊で移動しながら旅を楽しむ人にとって、もっと動きやすい寝袋はないかと人の形をした寝袋を開発しました。
つまり、人々のライフスタイルが変わっているのに旧来のメーカーはそこに視点がいっていない。当社はそのギャップに目をつけ2005年に自転車市場に参入しました。
―自転車の市場にもギャップがあった?
戦後、まだ自転車が普及していない時代に、自転車は移動手段として売られていました。その後ホームセンターが自転車の販売を扱うようになり、そこでは安くすれば売れたわけです。ところがもうほとんどの人に自転車が行き渡ってしまうと、安くしたところで買わなくなってしまいます。
かつての自転車は機能優先の考え方でつくられていました。よりよい変速機、ギア、クランク、ペダルをと考え商品がつくられていたのです。ところが消費者は、別に競技をするために自転車を買うわけではありません。そこで私たちはどんな状況で何のために自転車に乗っているかを考え、消費者が求めていてメーカーが気づいていないところへものを供給しようと考えたのです。
例えばドッペルギャンガーの商品はタイヤにラインが入っていたり、色が塗ってあります。色を塗るにはコストがかかりますし、それで走行性能が変わるわけではありません。しかし、動きにくくてもおしゃれな服を着るし、汚れるのがわかっていても白いシャツを着るように、消費者はかっこいい自転車に乗りたがっているのです。そのギャップに目をつけて自転車市場に参入しました。
―はじめての自転車市場の参入ですよね?何から始めたのでしょうか。
まず法規制を勉強しました。自転車は軽車両に該当するのでどういう法律があるのか、そして製品をつくるに当たっての工業規格も調べました。私たち新規参入の事業者にとってありがたいのはネットの普及です。製造してくれる工場を探すのに、海外の工場とネットで連絡をとることができました。また、設計・デザインについても少し勉強すれば扱える簡単なデザイン系ソフトが安価で手に入るようになっていました。以前であればかなりハードルが高かったことが門外漢のわたしたちでもできるようになってきたのです。車軸やハンドル、サドル、クランクの位置は人間の性質上決まってきますが、それ以外の部分については自由になるので、それをどう新しい形に落とし込んでいくか、海外の工場とやり取りしながら改良を重ねました。いかんせんこれまで見たことのないものをつくってもらうわけですから海外の工場とのやり取りは苦労しました。のこぎりを使ってある程度の形にしたものを送って、この形で作ってほしいというふうに伝えました。実際に市場に出すためにはおもりをつけて一定回数振動させて、耐えられるかどうかをみる振動試験をしなければなりません。安全性にこだわりながら、フレームの厚みなどを決めていきました。
―第1号商品は。
最初に出したのが102という商品で16インチのアルミ製折り畳み自転車です。当時、自動車に自転車を積んでアウトドアを楽しむ人が増えていたので、小径でコンパクトに折り畳める自転車が求められていると考え、開発しました。最大の特徴はパイプを二つ、つなぎ合わせたフレームの形状です。他社のフレームはダイヤモンド(ひし形)の形状をしているのでが、ドッペルギャンガーの商品は形状を見ればすぐそれとわかります。機能を追求するとどうしてもダイヤモンド型になるのですが、私たちはパッと見た時の差別化をめざしました。私たちは自転車をつくろうとして自転車をつくるのではなく、自転車に乗って何ができるのか、自転車に乗ってどんな満足感を得られるのかを考えるところからスタートしています。
その後も、健康に注目が集まった時には、速く走れるスポーツタイプの大径の自転車を開発し、またエコが注目され通勤用に使われ始めると、スーツに合ったデザインの自転車を、というようにニーズの変化を先読みし、ライフスタイルに合わせた自転車を開発してきました。
―販路はどうされたのですか。
新しい自転車をお店に持っていっても考え方が理解されず扱ってくれませんし、お店を通じて売ろうとするとそれだけコストもかかってしまいます。そこで私たちは当初から販路をインターネットに絞りました。どうすれば消費者がネットで買いたい気持ちになるかを考え、クリックして誘導したページでの見せ方にもこだわりました。他社の製品をネット上で見ると車体の写真に機能が記載されている程度です。これに対し、ドッペルギャンガーは本体の写真だけでなく、ブランドコンセプトをしっかりと伝える文字情報、そしてその自転車に乗った時のシチューエーションをイメージしてもらうため、自転車に乗っている人の写真も載せることで価値をつくりだしました。
―たくさんの商品を出される中でも強い支持を集めた商品は。
「202」です。最初は黒のデザインで出したのですが、ボルトやナットに至るまで可能な限り黒のものを使いました。そこまでしなくてもいいだろう、というところに徹底的にお金をかけたのです。駐輪場に何百台の自転車が並んでいたとしても、すぐにわかる存在感。実際に駐輪場で202を見かけて商品を扱いたいと声をかけてきた取引先もあります。商品そのものが広告塔になってくれていると思います。

―それぞれの自転車について開発のコンセプト、イメージをしっかり伝えた。
そうですね。それが伝わってコンセプトに共感された方に買っていただくことができました。そのようにして購入していただいたお客様はブランドの強いファンになっていただけます。ネット上でも商品ごとにファンクラブができていて、購入後に改造した全国のファンの皆さんが集まるオフ会は当社が把握しているだけでも7回行われています。それぞれのお客様が自分仕様の自転車にカスタマイズしています。例えば、もっと速く走りたいという方が変速機を変えたり、車輪を大きな径のものにしたり、より抵抗の少ない細いものにしたり、というように。そのプロセスも楽しんでおられますね。
―カスタマイズされることはかまわないのですか。
私たちは価格にもこだわっています。お金をかければそれだけ機能の優れたものはできますが、それは私たちの本意ではありません。皆さんに買っていただきやすい価格にしなければ手の届かないものになってしまうからです。こだわるところにはとことんお金をかけて、それ以外のところはできるだけコストを抑えたいので、おのずと限界が出てきます。そのコストをかけられなかったところをお客様がご自身でカスタマイズしているわけです。私たちがやりたかったことを代わりにお客様にやっていただけるので、私たちとしてはとても嬉しいことですね。ドッペルギャンガーのHP上では「ユーザーズバイクコンテスト」というコーナーを設け、お客様がカスタムされたものを投稿していただき競ってもらっています。
ドッペルギャンガーはドイツ語で「分身」を意味します。自転車はそれ自身では立つことができず、人が支えて初めて安定します。また、それぞれの乗り方がありその人の思考を映す鏡だと考え、ブランド名に思いを託しました。自転車が主役なのではなく、あくまで乗る人が主役なのです。
―価格戦略にも重きを置いているのですね。
より多くの人に買っていただき、楽しんでいただき、ドッペルギャンガーに乗る人が少しでも増えていくことで街中の風景が楽しくなると思っています。ユニクロが登場したことで、年配の方のファッションが底上げされたように、自転車も底上げしたいという思いがありました。今、価格は2極化しているといわれますが、私たちは、お金かける人とかけない人の間を狙いました。もう少しお金をかければこういう楽しみができるよ、と。同業他社がドッペルギャンガーのデザイン、色使いを真似てこられますが、お客さまもよく知っていて、これの本家はドッペルギャンガーだなと認識してくださっています。むしろ真似されることによって業界自体は活性化したのでよかったと思っています。私たちが新しい世界の扉を開けることができたのかなと自負しています。
―開発のアイデアはどこから生まれてくるのですか。
ブレインストーミングのようなミーティングをしてアイデアを膨らませています。自転車を取り巻く環境は常に変化していますから、その端緒をみんなで出し合いながら話し合います。自転車の乗る人が増えて自転車と歩行者の衝突が問題になっているからもっと安全にできないかとか、数年前は派手な色が好まれていたが最近はナチュラルなテイストが好まれているとか。あと今は防災が一つのキーワードになっていますので、長期間置いても空気が抜けにくいチューブとか、18リットルの灯油缶が載せられる自転車はないか、とか。
異なるアイデアが出るように、興味の対象が違う社員を集めて議論します。自転車そのものを突き詰めている人間もいますし、アウトドアが好き、音楽が好き、ファッションが好きな担当者もいます。ボーダーラインの服がはやるのを見越して、ボーダーのデザインの商品を出した時には、商品撮影時もボーダーシャツを着たモデルに乗ってもらい、おかげさまでヒットしました。数十万円の自転車を乗っている社員が、普段乗りできるセカンドバイクが欲しいといった時は、品質とルックスを維持し高級感を保ちながらもシンプルにした商品を出しました。どの部門の社員でもパートさんでも誰からでも受け付けるアイデア公募のシステムもあります。
―ネットに特化したことで他に取り組んだことは?
店頭で買う場合と違ってこちらから送り届けるわけですから梱包の方法も特殊な発泡材を使ったり、強度のある段ボールを使ったりしました。また、最終のところはお客様に組み立てていただくので、工具や付属品をわかりやすく並べるようにしたり、ネット上で組み立ての動画コンテンツを用意したりもしました。
―海外展開は。
海外へはオーストラリア、シンガポール、マレーシア、フィリピンなどすでに14カ国で売れています。営業は一切かけていないのですが、海外からどこに行ったら買えるのかとか、当社で扱わせてくださいと声がかかるのです。しかも販売される先々でファンクラブができています。これもネットに特化したがゆえの副産物なんでしょうね。
副産物で言うと、求人活動も有利になりました。以前では考えられなかったような全国の有名大学から応募が来るようになり、すごくありがたいですね。私たちの考え方、コンセプトにひかれ、こういうものをつくりたい、とおっしゃってくださいます。海外展開にしても求人にしても、コンセプトをしっかり持っているからこそなのだと感じています。
―ドッペルギャンガーでやりたいことはまだまだありますか。
まだカテゴリー的にも網羅できていないものがあります。婦人向けのいわゆるママチャリもそうですし、子ども仕様の商品も考えられるでしょうね。拡充できる要素はたくさんありますし、そこでギャップを探しながら開発をしていきたいと思っています。
これから取組みたいと思っているのはモノづくりの国内シフトです。今までは形やデザインで強みを発揮してきましたが、今後は例えば折り畳みの機構部、フレームを構成するパイプを1本につなぐブリッジの構造など基幹的な部品を国内で開発し、それを国内外の自転車メーカーに販売していきたいと考えています。幸い、私たちの会社はものづくりの集積地である東大阪に本社を置いています。東大阪でしかできない特殊な技術を活用してものづくりをし、何らかの利益を東大阪、日本に還元したいですね。アップルのスマホもiPadも日本の優れた技術でできた部品なしには完成品はできません。ドッペルギャンガーのこの基幹部品がないと自転車ができないというように持っていきたいなと思っています。
自転車市場は成熟市場と言われていますが、見方を変えればまだまだごろっとひっくり返すようなことができます。この仕事を続けていて改めて思うことは、モノが売れないのはお金がないからではなく、買いたいモノがないからであって、それをつくっていないメーカーに責任があるのだということです。今に満足せず、既存のメーカーでは到底考えつかないことにチャレンジし続けていきたいと思います。