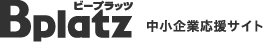最初わからんけど、そのうちフッと作り方が見えてくる

黒檀(こくたん)や紫檀(したん)といった硬く美しい銘木で手作りされた万年筆やボールペン。挽物師の技が生み出すこれらの工芸品は、使い込むほどに手に馴染む。
より高級感のある鹿角製もあり、「大人の文房具」として人気を博し、多くの雑誌やテレビなどで紹介されてきた。
作っているのは、平井木工挽物所の平井氏だ。

木製のペンは使うほどに手になじむ、まさに一生モノだ
挽物(ひきもの)とは、木材をろくろにセットし、回転させながら刃物を当て造形を施す技術、およびその製品。
弥生時代の遺跡の出土品にも、杯、鉢などの挽物が見られるという。屋号に挽物の文字があるのは、この伝統技術を長く残し、伝えたいという平井氏の思いからだ。

挽物の要となるろくろを囲む多彩な道具たち
平井氏がこの世界に飛び込んだのは、徳島から大阪に出てきた15歳の頃。大阪市生野区で挽物を営んでいた親戚のもとで修行を積み、23歳で独立した。
主な仕事は折り畳み傘の握り、化粧筆などメーカーから依頼されるさまざまな製品づくり。そんな平井氏の転機となったのが、約20年前、ある文具メーカーからの木製ペンのオーダーだった。

さまざまな素材でできたペン
「作れるか、と言われたから、作れますと答えた。最初どうやったらええか、わかってません。あれこれ考えてるうちに、こうすればええんや、というアイデアが浮かんでくる。仕事はそれの繰り返し」。

ろくろの回転軸をまっ直ぐに差し込むにも相当の熟練を要する
ペンに適した硬い木を板で仕入れ、角材に切断。それを機械に差し込んで丸い棒にする。それをキャップ、首軸、胴の3パートに切り分け、専用機で内部を空洞化すれば、いよいよ挽物工程になる。

シャカと呼ばれる道具でペン軸部分を丁寧に切削
ろくろに木材を取り付け、回転させながら鋭利な刃先を当て、薄皮を剥くような感じで少しずつ削っていく。ろくろの回転方向と速度は足で細かく調節する。
平井氏が手にする彫刻刀の刃先を湾曲させたような道具を「シャカ」と呼ぶが、その名の由来を尋ねると「はっきりしたことは知らんけど、お釈迦さんの手のひらを想像させるからやないかな」。

鋭利なシャカは1本1本、製品に合わせて手作りされる
仕事場には大小さまざまなシャカが並んでいるが、すべてが手作り。新しい仕事が入るたびに、製品に合わせてシャカを自作する。
挽物工程が済めばペーパーで磨き上げ、品質保持の塗料を塗り込み、ペン先などパーツを組み込んで完成となる。

削り上げたペン軸をさらにサンドペーパーで磨く
大阪ではほとんどいなくなった挽物職人だが、二人の息子たちが平井氏の後を継ぐ。「ろくろは回せるようになりましたが、シャカの作り方を教えるのはこれからです」。
昔ながらのふいごを使って真っ赤に燃えた炭で鉄を熱し、シャカを鍛造。平井氏の仕事場は、年に数回、トンカチの音が響く鍛冶屋に変身する。

代表の平井守氏
(取材・文/山蔭ヒラク 写真/福永浩二)