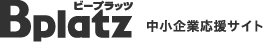【長編】何歳になっても「ありがとう」と言われ続ける。生涯現役のエンジニア集団をつくる。

大化物流開発合同会社は、2010年リーマンショック後のタイミングで立ち上がったソフトウェア開発会社だ。厳しい時代に産声を上げながらも、時代に流されることなく、いまも成長を続けている。
同社は「物流業界に特化していることを強く打ち出す」という、特殊な戦略をとりながら組織を大きくしてきた。設立4年目で、ニッチな業界をターゲットとしながらも、仕事が増え続け、人も辞めない組織をどのようにつくりあげているのか。代表の入江氏に訊ねた。
〉〉〉人材の流動が激しいソフトウェア開発業界において、「設立以来退社人数ゼロ」ですね。どのような工夫をしているのですか?
「退社人数ゼロ」については、気がついたら、誰も辞めていないという状況でした(笑)。当社は基本的に、俗な言い方をすれば、「利益が上がっていたら、何をしてもいい。」というスタンスをとっています。例えば、昼休みを2時間とってもいい。
社内においては、個々人がやるべきことをタスクリストに書いており、メンバー間でスケジュールと合わせて共有しています。「タスクリストに書いてあること以外はやってはいけない」というルールがあり、会社のミッションがスタッフ間で共有されているので、それに基づいて個人個人が考えて、行動してもらえばいいとおもっています。特に私が何かを仕掛けて、誰もやめていないということではなく、結果的にそうなった、という感じですね。
〉〉〉「経営理念」ではなく、「ミッション」なんですね。
「どうあるべきか」ということ、理念は、社員ひとりひとりが納得して、それを実践することが大切だと考えています。ミッションは、最初、会社設立前にスターティングメンバーで話し合い、仕事に関係なく自分たちの願望として「人としてどうなりたいか」という考えをまとめてつくりました。いまでも、スタッフ全員で毎月のミーティングを通して、見直しをしています。
会社は「何かをするための道具」にすぎず、社員それぞれが何をしたいか、何を提供したいかを考え、それを実現することが会社の目的だと思うのです。だから、いわゆるトップが考える「経営理念」ではなく、スタッフみんなが考えた箇条書きの項目が並ぶスタイルになりました。
そもそも、社員それぞれの「いまの立ち位置」や「自分の状況」によって、仕事への目線や考え方の次元が違いますよね。「何のために仕事をするのか」ということを、一人一人が考え、それをミッションに反映させて共有できれば、理念を会社が教える必要もなく、自然に浸透するものだとおもいます。
〉〉〉これらのミッションの項目の中で、一番大切にしている項目はどれですか?
ミッションに掲げている項目は、上から順番に重要度が高く、最初に掲げているのが「お客さんからの ありがとう がうれしい。」なので、お客様に感謝される仕事をすることが一番大切だと考えています。そのような仕事をするには、ちゃんと現場レベルでものをみて、ちゃんと現場を改善しないといけません。「こういうお客さんがいるから、こういうものをつくる」という視点でシステムをつくる必要があるのです。
当社では、物流の仕事において、なるべくシステム開発を提案しないようにしています。お客さんのことを考えると、システムは必要最低限でいい。どうしても、というところだけでいいからです。例えば、棚の位置を変えることの方が場合によって効果があることもあります。
意味のない、お金だけのやりとりはしたくないのです。つくったものをちゃんとお客さんにつかってもらって、「ありがとう」といってもらえることがエンジニアにとって一番うれしい、そう考えています。
〉〉〉実のある仕事はモチベーションにつながりますよね。組織として、社員のモチベーションの維持について工夫していることはありますか?
「人で固まった組織化」をしない、というのが我々のテーマにあります。受託開発の業務においては、プロジェクト毎にメンバーが組まれるスタイルで、スタッフが「自分はこの分野をやりたい」と思えば、そこに名乗り上げて、やりたいことができるようにしています。
社員はプロジェクトの掛け持ちも可能です。プロジェクトを横断して、自分が追究したいことができます。いまはまだ、試行錯誤しながらやっている段階ではありますが、各人が自分のやりたいことを優先できるようにしていきたいと考えています。
〉〉〉エンジニアがシステム開発を続けるには、年齢の問題もあるかとおもいます。この点についてはどのように考えていますか?
派遣の業務形態が多いソフトウェア業界における問題のひとつとして、プログラマがあちこち派遣先を転々として、「結局、何が残るのか」という状況に陥ることがあるかと思います。違う業界の職場を転々とすることを余儀なくされたプログラマは、40歳を過ぎると仕事がなくなってくるんです。
プログラマから、次のステップに上がるには業界の知識が必要となるのですが、派遣先を転々をしていると、運が悪いと、ノウハウを詰めないままとなります。私は現役プログラマ時代にそうした光景をみて、自分の会社では、プログラマがずっと働きづけられる環境をつくろうと思いました。当社が業界に特化しているのは、それが大きな理由です。
いま、当社で一番年齢が上の社員は55歳で、SE兼プログラマをしています。業界のスペシャリストになることで長く働くことができ、経験に基づいたアドバイスは、クライアントにもメリットをもたらします。
プログラマはずっと勉強をしなければならない職業。でも、それを続けられるのは、お客さんからの感謝の気持ちがうれしいから。スタッフが40歳を超えてからも、これまでの経験を強みにして、お客さんからの「ありがとう」をもらえる仕組みをつくることが、当社の企業としてのミッションだと考えています。
〉〉〉業界に特化することは、反面、限界をつくることにもつながりませんか?そのリスクはどのようにお考えでしょうか?
確かに業界を絞ると、キャパシティが限られます。ただ、当社の場合、物流業界で培ったノウハウと課題解決のスキルをエネルギー業界において応用することができました。
弊社では、国土交通省の「まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業」にて、モデル事業構想に策定されました。物流スマートシティとしてのモデル構想です。まだこれからの試みではありますが、物流もエネルギーも「コストの世界」。距離を縮めるほど、コスト削減が可能です。本質的な課題が似ている場合、他業界でも通用するので、物流業界に特化したことがリスクとなっていないのが現状です。
また、すこし話がそれますが、「リスク」そのものの捉え方で言うと、当社は、敢えてリーマンショックの直後に立ち上げた経緯があります。一番最悪の状態でスタートすれば、あとは上がるだけですよね。当時、会社設立のタイミングについては周りから、「あと半年待て。いまはやめておいた方がいい」という声もあったのですが、私はそのリスクがあるからこそ、逆に「このタイミングや!」と押し切ってしまいました(笑)。どんなことも、リスクがあって、ひとつひとつの目標をクリアできるから、楽しいんだと思います。絶対安全なことをしても、飽きてしまいますよね。もちろん、仲間がいるから、楽しめているのですが。設立時にリスクが非常に高いタイミング、つまり最初が崖っぷちだったので、チームワークの醸成にもつながりましたし、経費の使い方などは、いまでも貧乏癖が身についていますよ(笑)。
〉〉〉とはいえ、景気がよくない時代背景からの起業。転機はありませんでしたか?
それをいうなら、毎年、転機です(笑)。でも、自分はラッキーだとおもっています。常に、「自分はラッキー」と思っていると、苦労をしていても、いつかよくなるタイミングがあるので、その時に「自分はラッキー」になるんです。数撃てばあたるというか(笑)。大切なことは、手を止めないこと。ずっとやり続けることが大事なんだと思います。
〉〉〉そのマインドは、起業においては特に大切ですよね。これから起業する方や起業したての方に、一言アドバイスをするとすれば?
以前にデザイナーさん向けに、起業についての講義をしたことがあるのですが、多くの方が、起業をして「新しいことをしたい」「かっこいいことをしたい」ということをおっしゃっていました。その気持ちもわかるのですが、私は「自分が何をしたいか」ということさえ忘れなければ、無理をして「新しいこと」をしなくてもいいのではないかな、と考えています。
他の人が儲かっているビジネスに倣って、同じことをすることがカッコ悪いと思えたとしても、食べること、事業を続けることが大切じゃないでしょうか。なので、片意地を張らずに、まずは、楽しく仕事ができればいいじゃない、というスタンスでよいのでは、とおもいます。
〉〉〉ありがとうございました。最後に、今後の展望について教えてください。
エネルギー事業では、先ほどお伝えしました「まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業」のプロジェクトに絡めて、今後展開をしていきます。
物流事業においては、3PLの倉庫を探せるポータルサイトを公開しました。全国の倉庫をお持ちの企業さんが、じゃんじゃん自分の存在をPRしてもらえるものを作りたいと考え、自社で制作しました。倉庫さんでも、ホームページを持っていないところはありますし、もっていても、なかなか検索には引っかかりません。でも、プラットフォームを作って、検索エンジンに引っかかりやすい仕組みを提供できれば、ポータルサイトをご利用いただく企業さんに機会を提供できますし、倉庫の情報を探すユーザーにとってもメリットがあると考えます。
今後も現場レベルでものをみて、エネルギー業界、物流業界の両方に、新しい価値を提供できるように、チャレンジしていきたいですね。