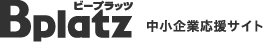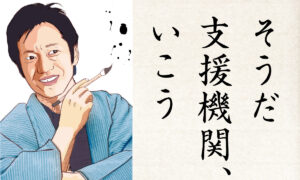世界50か国以上に寿司文化を届ける、業界最小の寿司マシンメーカー

回転寿司店からスーパーマーケットの寿司コーナーまで、身近に寿司があふれている日本では、自動でシャリを握る寿司マシンの歴史も長い。その先駆者のひとつが1972年創業の株式会社トップだ。経済成長とともに寿司の店頭販売が広がる中、同社は1976年に1号機となる巻き寿司マシンをリリース。以来、いなり寿司マシン、握り寿司用の寿司玉マシン、とラインナップを広げてきた。

世界最小&最軽量超小型握り寿司マシン“TSM-13”。
そんな同社が海外市場を開拓する契機となったのは、アメリカから届いた一本の依頼だ。現地の知人を介して、スーパーマーケットに食品を卸す会社から寿司マシンのオーダーを受けたという。1997年には、北米への機械輸出に必要な認証を取得し、同社の製品はついに海を渡る。ただし、この時は海外市場の拡大にはつながらなかったという。
「当時はまだ海外で寿司がポピュラーではなく、日本食レストランで職人が握った寿司を食べるのが一般的でした」と代表の玉置氏は振り返る。潮目が変わったのは2005年頃のこと。「オーストラリアで寿司マシンが売れているらしい」という噂を耳にし、現地を訪れた玉置氏が目にしたのは、多くの人が手軽な軽食として手巻き寿司を買い求める光景だった。

代表取締役 玉置 正彦氏
日本の企業が仕掛けたわけでもなく、海外で独自に進化した寿司文化。その様子に商機を見出した同社はオーストラリアへの輸出に力を入れ、そこから海外販路の拡大が始まる。そして2010年代に入ると、健康志向の高まりや和食のユネスコ「無形文化遺産」登録、マンガ・アニメ文化の波及といった追い風を受け、世界中で寿司人気が上昇。その波に乗るかたちで、同社も販売先をアジア、ヨーロッパ、南米へと拡げていった。

ハンドロール( 手巻き寿司)が並ぶオーストラリアの惣菜店。
「近年は日本人だけでなく、海外の人が別の国へ移住して日本食レストランを開くケースも増えています」と語るのは、海外営業を担う石井氏。特に経済成長の著しい東南アジアや、世界中から高級食材が集まる中東には大きなビジネスチャンスがあり、実際に引き合いも増えているという。

海外営業部 石井 亨氏
現在、販売先は50か国を超え、今や同社の売上げの約7割は海外販売が占めている。順風満帆に市場を開拓してきたように見えるが、その裏に地道な努力があるのは言うまでもない。「国によって認証の基準や電気の規格が異なるので、国ごとに仕様を変える必要があります。認証に必要な書類はすべて英語なので、翻訳ソフトがない時代は本当に苦労しました」と玉置氏。また、顧客によって使う米の種類や求めるシャリの硬さ、サイズなども異なるため、設定を細かく調整できるよう改良を重ねてきた。

ブラジルの大手スーパーマーケットのバックヤードで活躍する寿司マシンと、ホットロール。
「売上げが伸びる一方で、開発費もかかり続ける」と笑う玉置氏だが、創業から半世紀以上にわたり改良の手を止めてこなかった姿勢こそが、現在の成長につながっている。「日本は寿司の品質に対する要求が世界一高い。その日本でニーズに応え続けてきた経験が海外展開でも生きています」。
さらに玉置氏は、こう続ける。「将来的には技術そのものを輸出して、現地生産ができる体制を築きたい。そうすれば寿司マシンがさらに世界中に広がり、それに付随して日本の食材や調理技術への新たな需要が生まれるはず」。現在、日本に数社ある寿司マシンのメーカーの中で最小規模の同社だが、早くから世界で勝負してきたからこそ描く夢は大きい。

(取材・文/福希楽喜 写真/福永浩二)
株式会社トップ
代表取締役 玉置 正彦氏
海外営業部 石井 亨氏
事業内容/業務用米飯加工機器の開発・製造・販売(寿司ロボット・ 巻き寿司マシン・おにぎりマシン等)