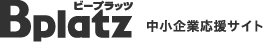《講演録》正解のない時代を突破する「挑戦する経営チーム」のつくり方
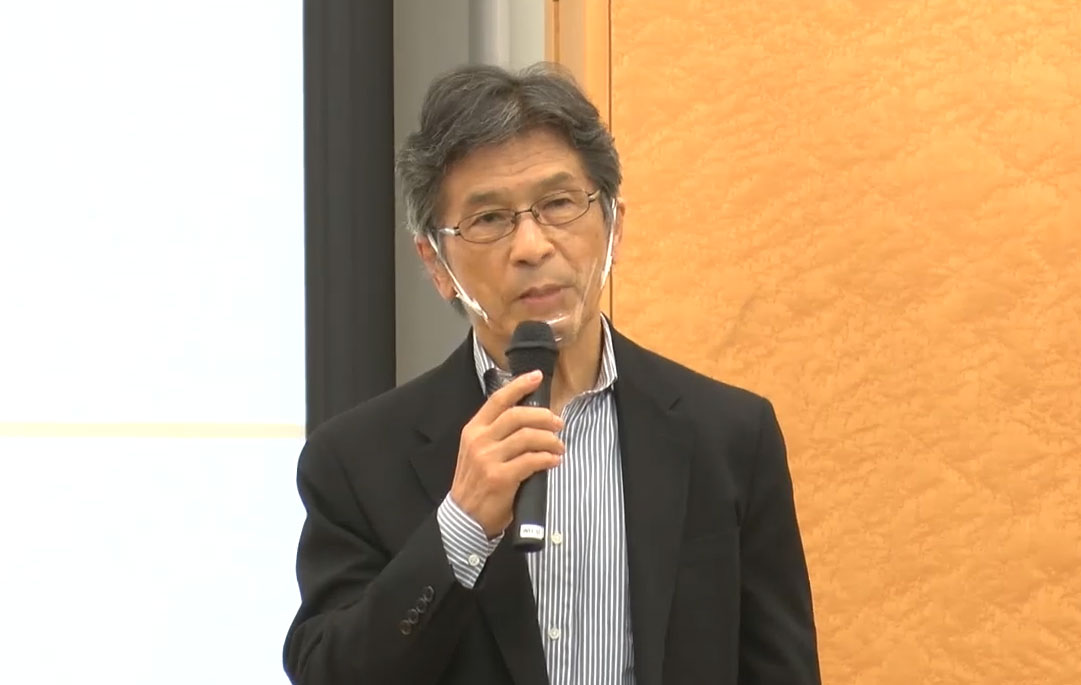
♦平成以降は調整文化のマイナス面が顕著に
調整文化は高度経済成長時には非常にプラスに働きました。組織への忠誠や序列意識が前提で、明確な前提のもとで「どうやるか」さえ考えていれば答えは出やすかったからです。そうして鍛え抜かれ積みあがったノウハウが日本の強みとなっていました。
しかし平成以降は調整文化のマイナス面が顕著になってきました。組織への忠誠はしょせん建前でしかありません。
アメリカの調査会社ギャラップ社が2017年に発表した調査結果によると、日本の熱意あふれる社員の割合は調査対象139カ国中132位の6%という割合でした。
なお、世界の平均値は15%、トップの米国・カナダは31%でした。序列意識の強さはジェンダー格差にも影響し、世界との差は拡がるばかりです。
私はシンガポールでもビジネスを展開していますが、そこでのメンバーの年齢・性別・国籍は非常に多様です。それだけ多様なメンバーが集まると問題もいろいろと出てきますが、今の日本企業では経験したこともないそのような問題に対処することも難しいでしょう。
過剰な調整文化は問題の先送りという思考停止をもたらします。社員は無意識のうちに傍観者や評論家のような言動をとり、不満を述べながらあきらめ感をもって黙々と仕事をこなしています。
残念なことに日本の2019年のひとり当たりGDPは、1989年に比べて1.6倍でしかなくG7の中で最下位です。調整文化のマイナス面をなんとかしないと日本は世界から取り残されてしまいます。
♦調整文化と対照的な「挑戦文化」と、日本人の強みである「共感力」
調整文化から抜け出すためのヒントとなるのは、私たちが20年ほどお手伝いをしてきた名古屋のある企業です。この会社では役員全員が本部長を兼任し当事者として経営と向き合っています。また、部門横断で例えば「社員満足度とはなにか」という答えのない問いについて何年も議論を重ねています。
このような取り組みによって考える習慣がつくのはもちろん、取り組みを通じてお互いがどんなことを考えているかを知り、案外自分と同じことを考えているのだと気づき互いに共感が生まれます。
会社の未来を拓くために必要なのは当事者です。当事者とは「会社が変わりうるということをあきらめていない人」を指します。
あきらめて環境に流されてしまうのは簡単です。脳卒中で倒れて入院患者さんを車椅子で介護した場合8割の方はいずれ寝たきり生活になりますが、自立歩行をサポートしながら介護した場合には8割が歩行可能な状態で退院できるのだそうです。
あきらめないことは本人のためでもあるのです。先に紹介した企業ではさまざまな自主活動に取り組んでいますが、会社のためではなく自分のためにやるのだという意識を強くもっています。
このような企業文化を私たちは調整文化とは対照的に「挑戦文化」と表現し、中国やアメリカでは挑戦文化が当たり前になっています。
日本でも高度成長期を支えたモノづくりの現場には、自分の頭を使って自分は何をすべきかを考える挑戦文化が存在していました。トヨタはその典型です。
「トヨタの社員は金太郎飴だ」と表現されることがありますが、これは枠にはまった飴ではなく軸を共有した金太郎飴なのです。
判断軸を共有しながらもそこには自由度があります。同様に日本の挑戦文化の根底には日本人ならではの共感力があります。他者の中に自分と同じ何かを探す力に日本人は長けており、自分をさらけだすことで警戒心が解かれ連帯感が生まれます。
例えば先輩・後輩といった概念はドイツにはありませんし、リレー競技における日本の強さは世界中で知られています。
次ページ >>> 共感力を生かすためには経営幹部がまずは当事者になる